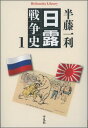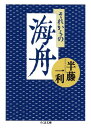まさにそうであった。東京大空襲により首都東京が焼け野原となり、広島・長崎に原爆が
投下されてもなお、日本は降伏する決断ができなかった。連合国からポツダム宣言が出さ
れでも、当時の最高戦争指導会議でも閣議でも、降伏の決断をすることができず、最後に
は御前会議を開いて、その決断を天皇に丸なげした。そして、天皇が降伏の決断をしたに
もかかわらず、それでもなお、その天皇の決断を受け入れられない閣僚がいて、再度御前
会議を開き、再び天皇に決断を仰ぐというありさまだった。しかも、当時の憲法上におい
ても、天皇には決定権があるのではなく、単に閣議等で決定したことを追認するだけの立
場だったのである。
それでもなお、陸軍の中には降伏を認めたくない者たちがいた。表向きは「国体を守る」
ためと言いながら、軍人としての自分たちのメンツ、組織のメンツを守りたかったのであ
る。そこには国民のことなど眼中にはなかった。
そのような日本軍部の背景には、「生きて虜囚の恥ずかしめを受けず」という言葉からも
わかるように、それまで敗戦の経験がなく、敗戦や撤退ということについて、まったく考
えない精神構造になっていたことがあったと想像する。日本軍部は、クルマで言えば、バ
ックギアがないクルマだったのだ。しかし、これを単に軍人の暴走だと片付けることはで
きないように思う。彼らは軍隊という特殊な環境のなかで、そういう精神構造へ徹底的に
仕込まれてきたのだ。そして、これはかつての日本軍だけの特殊な問題とも片付けてよい
のか、現代の組織にも通じるものがあるのではないのかと思える。
この本を読んで、あの8月15日の終戦の日を迎えられたのも、ほんとに危機一髪状態だ
ったんだと、つくづく思った。
「美しい日本の精神を取り戻す」この安倍首相が使ったこの言葉は、あの8月15日の終
戦に反対してクーデターを起こした日本軍青年将校からも発せられた言葉であった点に、
我々はしっかりと注視しなければならない。
・今日の日本および日本人にとって、いちばん大切なものは「平衡感覚」によって復元力
を身につけることではないかと思う。内外情勢の変化によって、右に左に、大きくゆれ
るということは、やむをえない。ただ、適当な時期に平衡を取り戻すことができるか、
できないかによって、民族の、あるいは個人の運命がきまるのではないか。
プロローグ
・7月27日のポツダム宣言が東京の中枢神経を震撼させた。海外からの電波は巨大な楔
を日本の歴史にうちこんできたのである。多くの関係者は突然のようでもあり、当然来
るべきものがきたと感じながら、ポツダム宣言を受け止めた。
・東郷外相が天皇に報告した。思い沈黙が流れたあと、やがて天皇は言った。「いろいろ
議論の余地もあろうが、原則として受諾すほかはあるまいのではないか。受諾しないと
すれば戦争を継続することになる。これ以上、国民を苦しめるわけにはいかない」
・ポツダム宣言は、そのおわりに厳然と声明している。「われらは右条件により離脱する
ことなかるべし」。つまりは、それ以外にはいかなる交渉にも工作にも応じないという
のが連合国の意志であった。にもかかわらず、最高戦争指導会議でも閣議でも、これを
「最後通牒」とみなした者は一人もいなかった。
・翌28日の各朝刊紙は内閣情報局の指令のもとに、ポツダム宣言を国民に発表した。そ
して、国民の戦意を低下させぬようにという配慮から、かえって紙面には戦意昂揚をは
かる強気の文字があらわれた。読売報知は「笑止、対日降伏条件」、朝日新聞は「政府
は黙殺」、毎日新聞は「笑止!共同宣言、自惚れを撃砕せん、聖戦をあくまで完遂」と
壮語した。
・政府は外交工作と軍の旺盛なる抗戦意識の間にはさまれて、両立しえない事態に立つこ
とになった。鈴木首相はポツダム宣言についての見解を記者団に尋ねられて「あの共同
宣言はカイロ会議の焼き直しであると考えている。政府としてなんら重大な価値がある
とは考えていない。ただ黙殺するだけである。われわれは戦争完遂に邁進するのみであ
る」と述べた。だが、対外放送網を通して全世界に放送されたとき、このロボット的発
言が日本の首相談として重大視されてしまった。そしてこの「黙殺」が、ついには外国
の新聞では「日本はポツダム宣言を拒絶した」となって報ぜられた。そしてのちの原爆
投下やソ連の対日参戦を正当化するための口実に使われたことはよく知られている。
・ポツダム宣言を受諾するほかに日本を救う道はなかったが、政府も統帥部もそうは考え
なかった。
・天皇は、たった一発で広島市が死の町と化したという報告を受けた。天皇は顔を曇らせ
たが、それ以上はたずねようとはしなかった。
・阿南陸相に、陸軍部内からの突き上げは時々刻々と激しさをました。陸相は、全国に戒
厳令を布き、内閣を倒して軍政権の樹立をめざすクーデター案を密かに提示されていた。
しかし阿南は動かなかった。
・御前会議において、天皇は腹の底からしぼりだすような声で言った。「空襲は激化して
おり、これ以上国民を塗炭の苦しみに陥れ、文化を破壊し、世界人類の不幸を招くのは、
私の欲していないところである。私の任務は祖先から受け継いだ日本という国を子孫に
つたえることである。いまとなっては、ひとりでも多くの国民に生き残っていてもらっ
て、その人たちに将来ふたたび起ちあがってもらうほか道はない」。
・「どうも国を救うのは鈴木内閣だと思う。だからオレは、最後の最後まで、鈴木総理と
事を共にしていく」と阿南陸相はしっかりと言った。
・重臣会議が開かれた。ほとんどの重臣は、天皇制の存続さえ保証されるならポツダム宣
言受諾に異議はない、と政府の方針に賛同したが、陸軍出身の元首相の小磯国昭と東条
英機はそれを不可と反対した。
「わが屍を越えてゆけ」−阿南陸相は言った
・8月14日正午、日中戦争開始よりこの日まで戦死者は陸軍148万2千人、海軍45
万8千人。一般国民の死者100万人。何百万戸もの家屋の崩壊。「日本帝国の破壊」
をもって古い歴史は終わろうとする。人、機械、軍需、資源すべてにおいて最初から不
利であったが、勝利をつかもうとする不屈の闘士によって、戦争はこの日までみちびか
れてきた。個人的な決意の問題ではない、国民全体の意志の表現であった。
・阿南陸相のうちにある軍人精神が「降伏」や「退却」を許さないのである。国土を占領
され、武装を解除され、戦犯がつぎつぎの処罰されるという状態で、「国体」をいかに
して護ったらよいというのか。あまりにも屈辱的な条件をのむより「最後」の一人まで
戦う」ことによって、敵に大打撃を与え、少しでもよい条件において「休戦」すべきだ
とする信念を、ますます強固にした。
・竹下正彦中佐は、全陸軍が一丸となって最後の一兵まで戦えば、かならず死中に活をう
ることが可能であろうと考えた。
・再度の天皇の聖断による降伏決定は陸軍に対する国家全体の不信任を意味すると言って
いいだろう、絶対絶命なもので、帝国陸軍は孤立無縁、戦争に対するその重要な役割は
終わった。しかし、支柱たる陸相は幻滅を感じず、狂気にもおちいず、むしろ堂々とし
ていた。
・竹下中佐は、全陸軍には最後の手段が残っていることを思いついた。陸相の辞職である。
なぜなら御前会議の天皇の言葉によって、降伏が最終的に決定されたわけではないから
である。つまり御前会議は憲法上の正式機関ではない。ただ単に天皇の御前で政府と総
帥部の連合会議が行なわれ、天皇の御意志の発表があったというだけのことであり、法
制上の建前としては閣議で満場一致でこれを決定しなければ、国家意志とはならなかっ
た。誰か閣僚一人が天皇の言葉いかんにかかわらず最後まで反対し、不一致を理由に辞
職したとすれば、内閣は倒れてふりだしにもどり終戦は不可能になる。
・海軍の軍令部次長の大西は「もしお上が終戦せよと仰せられた場合は、たとえ逆賊の汚
名を着せられても、大きな正義のためあくまで戦争を続けねばならない」と言った。
・10日の陸相訓示「たとえ草を喰み、土をかじり、野に伏するとも、断じて戦うところ
死中自ら活あるを信ず」
・阿南陸相は忠誠な軍人であった。義務に忠実な将軍であった。これ以上反対することは
臣下の不忠行為であり、彼の中の鍛えられた軍人精神がなによりも承服しがたいことで
あった。いわんやクーデター計画を推進するなど、不忠不義の汚名を末代まで残すにす
ぎないのである。いまこそ自分の心をいっそう明確にして、青年将校たちのはやる心を
おさえねばならない大責任があった。阿南陸相は言った「星団は下ったのである。いま
それに従うばかりである。不服の者は自分の屍を越えてゆけ」
・天皇は御前会議で言った。「自分はいかになろうとも、万民の生命を助けたい、この上
戦争を続けては結局、わが国がまったく焦土となり、万民にこれ以上苦痛をなめさせる
ことは、自分としては実に忍び難い」。
・最後の決意を確認して死にもの狂いで活動していた青年将校たちは、ほとんどが魂を抜
かれたようにぼんやりとし、それぞれの席に座して窓外を流れる真夏の白雲を眺めやっ
た。あるいはひたすらに悔し涙にくれるものもあった。
「録音放送にきまった」−下村総裁は言った
・昭和19年は米が不作であり、ために20年夏にはひとりの標準配給食料を減らさざる
を得なくなったのである。1日2合3勺を2合にしようというのである。この1割減は
必死の強行策である。もし2合3勺を保持していれば、8月一杯ぐらいで日本国民は明
日の食なみ流浪の民となり、新米のとれる10月までには国民総餓死になってしまう。
2合3勺といい2合という、いずれにせよ机の上の配給量であった。実際には末端の口
までは容易に届かず、遅配欠配の連続であり、腹をへらしながら本土決戦に狂奔する頭
上に焼夷弾が雨ふるのである。
・建軍いらい敗戦を知らず、また生きて虜囚の辱めを受けずと教育された陸海軍第一線に、
敗戦のなんたるかを知らせるのはたしかに大変な問題であった。
・この終末期において、本土決戦を強調し、本土決戦を敢行することによってこそ日本が
さいごの勝利をうると結論し、あらゆるものを挙げて本土決戦に振り向けようとし、ま
た着々実行してきたのは陸軍であった。
・天皇の聖断がどうであろうと、陸相がどう決断しようが、また軍全体の意志がどうなっ
てゆこうと、自己の信念に忠実に生きんとする血気の軍人が活動を開始し、次第に歴史
の表面に躍りでようとしていた。
・大きな歴史の流れに抗するには、断固たる決意と、正しかろうが間違っていようが、そ
れを問わない愛国的純情、それに決死の覚悟が必要であろう。
・小園大佐は「たとえ刀折れ矢つきても、生命のあるかぎりは石にかじりついても、陛下
と国土を守るべきである。私は独力でも抗戦を継続する覚悟である」と論じた。
「軍は自分が責任をもってまとめる」−米内海相は言った
・敗戦は亡国ではない。しかし最後の場面における内戦は亡国に通じるであろう。そのた
めに陸軍の方針を絶対のものとしておかなければならなかった。
・「大御心」とはなにか、「国体の精華」とはなにかという大命題にとっくんでいた。真
剣に、それは殺気だつほどの真剣さで。しかし真剣すぎるだけに狭かった。彼らが大命
題にとっくんでいる土俵がつまり「軍人精神」というワクであるのに、彼らは気づいて
いなかった。彼らは教育されていた。全滅か、もしくは勝利あるのみと。彼らに降伏は
なかった。陛下を奉じて戦えば、たとえ全滅するもそれは敗北ではない。そうした神秘
的な、しかし徹底した観念を吹き込まれていた。
もし天皇の上に他の外力が加わったとしたら、国体護持は絶対不可能である。この外力
を排除するものが皇軍の力であり、皇軍の任務はそこにあるのである。ところがポツダ
ム宣言受諾は、とりも直さず天皇の上に他の力が加わることであり、この力を取り除く
ことを任務とする皇軍は武装解除されている。これでどうして国体護持ができるという
のか。全滅か、もしくは勝利しかないというときに、そうした妥協的な国体護持という
ものがありうるであろうか。古今東西の歴史に妥協的な講和というのはあり得なかった。
とすれば、陸軍はむしろ一億玉砕するにしかずとの態度をとるべきである。
・はたして降伏することが真の大御心であるかどうか。敗北主義の重臣が勝手にきめ、気
弱になっている天皇皇后に無理やり承知させたことではないのか。天皇にして大元帥の
御心はそうではないはずである。戦争に疲れはて命の惜しくなった重臣の心が、真の愛
国心を凌駕し去ったのではなかろうか。
「永田鉄山の二の舞だぞ」−田中軍司令官は言った
・連日連夜のごとく襲ってくる敵機の空襲のもと、軍隊の方がかえって安全で、戦力もな
く所属もない国民こそが火の海をさまよわねばならないという悲劇的な矛盾に突き当た
っていた。個人の力ではなんともならぬ末期の現実であった。軍人という職責をはなれ
て客観的に判断すれば、終戦のほかに救国の途はない。そうした実情を知るだけに、聖
断にそむき軍が蹶起したところで、国民はついてこない。
・陸海軍4百30万、特攻機1万、海上特攻兵器3千3百、それが日本国内いたるところ
で最後の一大決戦にそなえ待機し、しかも、彼らは挙軍火だるまとなり全滅をかけて戦
うべき訓練され、士気を鼓舞されてきた。指揮する陸軍統帥は、戦争全期間を通して陸
軍が戦ったのは小さな島嶼戦ばかりで、それに敗れたのは単に補給戦に敗れたからであ
り、本格的な十数師団が正面からぶつかりあう陸上作戦となれば、むざむざと敗れるこ
とはないと豪語してきた。それが一戦も交えずして、敵と呼んできた相手の手によって
一夜にして武装解除させられるとは、武人として軍隊として千秋の恨事であろう。生き
恥をさらしてなんになるかという熱情が狂気を生み、軍に不測の騒ぎが起こらぬという
保証がどこにあるのか。
・軍の大方針は承詔必謹ときまったが、内容は、戦いに敗れたということ、軍はおとなし
く武装解除されるということだけで、どのようにしてそれが行われるのか、方法や時期
その他について想像をめぐらしてみたところで、確たるものを描くわけにはゆかなかっ
た。歴史始まった以来、はじめて体験する破滅のときなのである。
「どうせ明日は死ぬ身だ」−井田中佐は言った
・阿南陸相が聖断に従うと決意したとき、成否は決したのである。軍人としての理解力と、
普通人としての正常な感覚はそれを教えている。もはやとうとうたる時流の挽回は不可
能であり、ふり上げた拳のやり場に困り、それですごすごと頭をかいてひき下ったり、
自棄にになってふりまわしたりすることより、堂々と、世界中の注視をあびながら手を
おろす方が真の勇気というものであろう、そしてのこされた道は、いさぎよくその命を
絶つことだけである。
「近衛師団に不穏の計画があるが」−近衛公爵は言った
・大多数の忠誠な将校たちにとって、陸軍の崩壊は彼らの思想、信念の根底までを揺さぶ
り、彼らははじめて内面の戦いに直面した。終戦にさいしどうあるべきか、なにをなす
べきかにまよい、おのれの道を失っている者が多かった。忠誠とはなんであったか。こ
れらの部下たちを絶望的な混乱から救い、身をもって正しい決断に導くために、陸相は
必死に努力を傾けている。なにより彼らに、「栄光ある敗北」を与えてやらなければな
らない。
・なぜもっと早く戦いをやめることができなかったのか、それは明らかに政府当局や重臣
たちの怠慢であり、無責任のためであろう。天佑神助を信じ、偶然を頼み、特攻隊の死
力にすべての望みをかけて、誰ひとり敗北の責任をすすんで引き受けようとしなかった。
そのため、国民の数十万はいたずらに戦火に死し、住居は灰燼に帰した。そしていま天
皇に力によってやっと終戦ときまった。天皇に全責任をかぶせることで彼らは責任を巧
みにごまかしたのではないか。
「時が時だから自重せねばいかん」−蓮沼武官長は言った
・東条英機大将は、戦争犯罪人の問題について陸相に語った。「いずれ降伏となればわれ
われは当然のことながら軍事裁判にかけられるだろう。そのときは堂々と大東亜戦争の
意義について述べよう。われわれは防衛戦争を戦ったのである」
「軍の決定になんら裏はない」−荒尾軍事課長は言った
・この時期ほど「国体」が問題にされたときは日本歴史はじまって以来なかったであろう。
彼らばかりでない。幾度、幾十度、幾百度、何千何万の人が「国体」という言葉を口に
したかしれなかった。しかしその内容としてはなにが考えられていたかとみれば、千差
万別、その顔の異なるように変わった。抽象的に高唱された場合があり、もっと具体的
な意味を持った時もある。だがいずれにせよ、その言葉が非常に大きな力を持っていた
ことは事実であった。
・青年将校たちは、天皇が自分の身はどうなってもよいと言われたことに対し、強く反発
した。現人神としての天皇の神性は、有史以来国民感情のなかに存在するものなのであ
る。それは国民はもちろん天皇ご自身も深く考慮されねばならないと彼らは断じた。承
詔必謹などという馬鹿げた方針は、皇室の形骸だけをのこして日本の伝統的精神を無視
するものなのである。皇室が皇室たるゆえんは、すなわち民族の精神とともに生き続け
る点にある、と彼らは思いつめた。政府も軍首脳も終戦の道を急いでいる。そのいうと
ころは皇室の存続であるが、彼らは無能な為政者の腹をさぐれば、真のねらいは国家の
面目よりも、物質的生活苦、ないしは戦争の恐怖に対する自己保全の利己以外のなにも
のでもない、と彼らはいいきった。
・青年将校たちはすべてが決定したところから幻影をもとめはじめたのである。判断力と
平衡感覚を失いはじめた。彼らは事態を絶対絶命のものと信じていなかったし、かりに
最悪の事態であったとしても、やはり起たねばならない。彼らには時の流れに対する悲
壮な反発があった。その悲壮感に酔った。国体護持を貫こうとする自分たちの決意こそ、
むしろ歴史の記録に永久に残るであろう、と。
「斬る覚悟でなければ成功しない」−畑中中佐は言った
・まとまってこそ陸軍は強力であったが、敗北、そしてこれ以上の抵抗の無意味さを認識
したとき、軍人はひとりひとりばらばらにされ、裸の人間として取り残された。そして
取り残されてみると、皇軍にも無条件降伏があるのだということが、決定的に、しかも
事実によって証明され、彼らの心に喰いいってきた。
・彼らの考えるところでは、戦争はひとり軍人だけがするのではなく、君臣一如、全国民
にて最後のひとりになるまで、遂行せねばならないはずのものであった。国民の生命を
助けるなどという理由で無条件降伏するということは、かえって国体を破壊することで
あり、すなわち革命的行為となると結論し、これを阻止することこそ、国体にもっとも
忠なのである、と信じた。
「それでも貴様たちは男か」−佐々木大尉は言った
・天皇を現人神として一君万民の結合をとげることが、すなわち正しい国体護持である。
それは国民的信仰といってもいいのである。それなのに、形式にでも皇室が残ればいい
とする政府の幸福主義に私たちは反対するのです。皇室の皇室たるゆえんは、民族精神
とともに生きる点にあるのです。形式ではないのです。形骸にひとしい皇室と、腰抜け
の国民と、国土さえ保全されればそれでいいという「政府の国体護持」は、つまるとこ
ろ皇室の名を利用する自己保全でしかないと看破すべきなのです。
・理屈はどうあろうと、聖断ひとたび下った今日、殿下のご意志に反する行動は絶対に許
さぬ。戦うも殿下の命によって、また退くも殿下の命によって、これが近衛師団たるも
のの本分なのだ。
・近衛兵は、宮城を護るのが任務であって、よしんば陸相や参謀総長の命令であろうと、
そこに籠城して混乱の渦にまきこむことは許されぬ。
・南米の小国パラグアイは五年戦争で人口の8割を失うまで戦いました。フィンランドし
かり、われわれの敵国である中国またしかりであります。ひとりわが国は神州生気の民
と自負しながら、本土決戦も行わず降伏せんとするのでは、あまりに打算的というほか
ない。このような中途半端で戦うことを止めるなと、玉砕し、特攻と散った英霊をあざ
むくこと、これよりはなはだしいものはない。「美しかるべき日本の精神を取り戻す」
ためにわれわれは蹶起します。
「東部軍になにをせよというのか」−高嶋参謀長は言った
・事件はあっという間であった。結末は素早く、残酷に、避けられないものとしてやって
きた。三人の将校が参謀長室に入り、畑中少佐が一言か二言会話をかわしたと思う、次
の瞬間に、少佐の合図を受けたかのように、上原、窪田が抜刀した。師団長めがけて畑
中のピストルが火を噴き、剣道五段の上原が師団長をけさがけに切り倒し、さらに畑中
少佐に組みついた白石中佐の首筋を上原がうしろから斬り、窪田少佐がとどめを刺した
という。
「二・二六のときと同じだね」−石渡宮相は言った
・あれほど強がり威張りくさっていた陸軍がおめおめとひっこむはずがないから、全軍叛
乱の知らせはかなり確実性が高いぞと説く人もいれば、詔書を出したというのも実は軍
の大作戦の一貫なのだ、安心して近寄ってくる敵を海岸で迎撃し、一大水際作戦を敢行
するつもりなのだという説もあった。
「斬ってもなにもならんだろう」−徳川侍従は言った
・「実は明日ポツダム宣言が受諾される。腰抜けの重臣たちが自分の生命を惜しむばかり
に、日本を滅亡させるのも平気で、これを発表しようとしているのである。発表されれ
ば万事は終わるのである。われわれの美しい祖国は滅びるのである」
・「祖国は滅びない。徹底抗戦を続けることでおのずから道は開けるであろう。発表され
た後ではそれすらも不可能である。鈴木首相はわが屍を越えてゆけと言った。軍政をし
いて戦いを続けよう」
「兵は私の心をいってきかせよう」−天皇はいわれた
・天皇は「兵を庭に集めるがよい。私が出て行って直に兵を諭そう。兵に私の心をいって
きかせよう」
「謹んで玉音を拝しますよう」−館野放送員は言った
・敗戦の罪はすべて陸軍が背負うべきであろう。統帥権の独立を呼号し、政治を無視し、
自分の意のままに事後承諾の形であらゆることを遂行してきた陸軍こそ、罰せられてし
かるべきなのであろう。
「ただいまより重大な放送があります」−和田放送員は言った
・外を見渡すかぎり瓦礫が堆積した焼野原である。かつての住居のあとに掘立小屋をつく
り、日本人は飢えた毎日を送っていた。塩を例にとってもあと一ヶ月もすれば牛馬に食
わせることができなくなるほど、窮乏のはての敗戦であった。形式などにこだわること
のない完全な敗北なのである。
・祖国を、美しき君臣一如の日本精神を、屈辱から救おうと決心し、宮城に籠り、それか
らのち、軍の先頭に立って、最後の一兵までの戦いを戦うつもりであったが、それは新
しい日本に受け入れられなかったのである。宮城前二重橋と坂下門との中間芝生で二人
の将校は命を絶った。