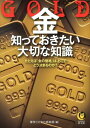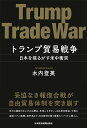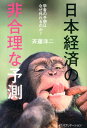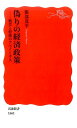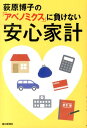「銀行預金から株式投資へ」ということに過ぎない。貯蓄はどんな形であれ、経済全体で
は必ず投資として使われるという。現在の日本が抱えている問題は、その貯蓄が減り始め
ているということだという。日本経済全体が、貧しくなり始めているのだ。それなのに、
今の政府が打ち出す政策は、目先の対策だけに終始している。
今、原油価格が暴落している。一時1バーレル当たり100ドル近くまでになっていたも
のが、30ドルを割る水準まで下落している。原油をすべて海外からの輸入に依存してい
る日本とっては、これはまさに「棚ぼた」だ。天からのめぐみだ。日本は、安い価格の原
油輸入が、あらゆる分野においてコスト削減となり、経済が潤うはずだった。
しかし、おバカな政府と日銀の、異次元の量的緩和政策による円安ドル高によって、その
めぐみに水を差している。何が何でもインフレ率を2%にするんだと、ガムシャラに突き
進む政府・日銀は、まさに「目的と手段」を取り違えていると言っていいのではないのか。
インフレ率2%を目標に掲げて3年にもなるが、未だに目標を達成できないでいる。
もはや、アベノミクスは間違いだったというのは、明白だと言ってよい。これ以上、この
政策を続けることは、「破綻」という結末しか待っていないのではないのか。
それなのに、今度は「マイナス金利」という奇策に出た。それにより、一時株価は少し回
復を示したが、その効果もたった2日間だけだった。これにより、「もはや来るところま
で来てしまったか」と多くの国民は思ったのではないのか。
日本における不景気は、将来の所得の不安、将来の雇用の不安、将来の政府への不安、不
信から来ている。いくらアベノミクスや異次元金融緩和というような、小手先の対策を打
っても、改善されない。ますます不安心理を増長させるだけである。今の安倍政権におけ
る異次元の量的金融緩和は、目先の経済のために、将来の蓄えまでも食いつぶしていく政
策だ。このままでは、日本はたいへんなことになる。しかし、もはや手遅れか。
・円安とインフレを起こしたい。その目的を達成し、消費者の生活を苦しくした。異常な
金融緩和は、ショック療法で株価をどん底から引き上げたが、金融市場はバブルとなっ
た。痛みを伴わない政策で短期にバブルを起こし、コストとリスクは先送りする。これ
がアベノミクスの本質だ。そして、日本経済はそのすべてのコストをこれから払うこと
になったのである。
・アベノミクスの効果が、今後、地方や中小企業など、これまで恩恵を受けていないとこ
ろに回るということはあり得ない。これからは、政策の影響は悪いものだけが増えてい
く。今、アベノミクスで良くなっていないところは、一生良くならない。そして、今後、
さらに悪くなっていく。
・しかし、日本経済は絶望的ではない。政策は悪いが、日本経済は悪くない。したがって、
日本経済自身悲観する必要はない。間違った政策を取り除けば、日本経済は自ずと力強
さを少しずつ回復していくのだ。
経済政策と政策論争の危機
・エコノミストなどの有識者は、政策担当者と人々の狭間で戸惑っている。株高、円安の
下での日本経済の好景気を歓迎しながらも、大幅円安でも輸出数量がいつまで経っても
伸びないことに首をかしげる。彼らは、輸出額は最初はむしろ減少するが、時間が経つ
につれて、円安効果により、輸出の量も伸びてきて、輸出金額はそのうち大幅増加とな
る。だから、最初は輸出が増えなくても当然で、心配することはない、と言っていた。
・しかし、アベノミクス登場から2年以上が経ち、今では、この話は正しくないことを人
々は知っている。工場の多くは海外に移転してしまったので、円安になっても輸出数量
は伸びないのは明らかだった。
・一方、輸入面では円安のデメリットは大きい。日本企業が日本市場で売る製品も海外生
産だから、円安により原価が上がっている。売上数量が減ることを承知して値上げをす
るか、価格を据え置いて利益を削るかの選択に迫られているが、利益は減少あるいは赤
字転落となった。
・現実の日本経済は、日本は今や大幅な貿易赤字を継続的に計上しており、輸出よりも輸
入が多い経済であるから、円安がデメリットとなる輸入のほうが多い以上、トータルで
は円安は日本経済にとってマイナスである、というのが中立的な事実認識だ。
・いわゆるリフレ派の人々は、インフィレを起こせば、日本経済の問題はすべて解決する、
という立場だ。そして、アベノミクスの金融緩和は素晴らしいが、消費税増税は最悪だ
った、消費税増税ですべてが台無しになった、マイナス成長はすべて消費税率を8%に
引き上げたせいだ、と主張する。日本経済は消費税率8%への引き上げにより景気が悪
化したのであり、消費税率引き上げは大きな失敗だったと考える人々は多く、安倍首相
もその一人であるように見受けられる。
・消費税率20%への引き上げの1年半の延期により、日本政府は財政への信任が失われ、
国債が暴落するという議論も、リスクを課題に主張している。2%の増税を1年半延期
しようがしまいが、日本政府の借金の額は長期的に持続不可能なまでに膨らんでおり、
長期にはいずれにせよ実質破綻が調整を迫られる。今さら6兆円程度借金が増えたとこ
ろで、すぐに破綻が起きるわけではない。
・一般国民は、アベノミクスが無意味で有害であることに気づいている。世論調査でも否
定的な意見が圧倒的多数だ。一方、首相、閣僚、政策担当者、そのブレーンたちの多く
は、ただ単に、アベノミクスは正しい、という誤った信念で政策を推し進めているだけ
なのだ。これは、より罪深いし、より絶望的な状況で、解決が難しい。
・多くの国民が、政策の欠陥を理解しており、他方、権力者とそのアドバイザーたちがそ
の誤りに気づかず、誤った政策に固執している。こんな悲劇的な国はめったにない。我
々はなんと哀れな国の哀れな時代に生きていることか。
日本経済はヤバくない
・GDP増加を「経済成長」と呼ぶ以上、GDPが増加しなければ「成長しない経済」と
いうことになる。日本GDPは、もはや増加しなくなっている。人口が減り、高齢化に
より労働力はもっと減っている。労働人口は今では全体の人口の半分に過ぎない。技術
革新も1980年代までのようなスピードでは進んでいない。日本社会と日本経済の成
熟に伴い、日本のGDP拡大能力は低下してきたのである。
・日本経済が成長しないのは、すでにGDPが拡大しない経済構造になっていたこと、そ
れにもかかわらず、それを無理に拡大しようとしたことが、かえってさらなる経済の縮
小をもたらしていること、この二つの理由によるのだ。
・異次元の金融緩和により株価はさらに急騰し、ミニバブルとなった。短期的には資産効
果により、消費が刺激され、富裕層、資産保有層の高額消費が膨らんだ。しかし、この
短期的な棚ぼたの一方で、コストとリスクは先送りされ、金融市場および日本経済は、
長期的には大きなリスクを抱えることになった。
・短期にも長期にも円安は、経済にマイナスである。そもそも、円安は自国通貨の値下が
りであるから、日本経済は円安より富を失う。我々の土地、株式、預金などすべての資
産が、ドルベースで見れば価値が失われている。実際、限られた我々の資産と所得で、
原油や天然ガスなどの資源、食料など、ドルで価格が決まっているものを必需品として
買うのだから、日本にある資産、おカネがどんどん失われることになる。
・リスクとして最も大きなものは、為替市場、国債市場の波乱の可能性が急激に高まった
ことだ。つまり、異次元の金融緩和によって、為替、国債の価格変動が急激に高まり、
将来これがどうなるのかまったく予測がつかなくなってしまった。サプライズを起こす、
ということは、将来にもサプライズが起こり得るのであり、金融市場に振り回されるこ
とが予想される。しかも、それは日本銀行があえで自ら行う金融政策によるものだ。日
本の金融機関、企業、個人は、今後とも金融政策に振り回さて、突然の変化に怯えてい
かなければならないのである。
アベノミクスの成功という日本の失敗
・アベノミクスは失敗していない。今が失敗だと思うなら、最初から間違っていたのだ。
あべのミクストは、痛みを伴わない短期の刺激策を集中して行い、コストとリスクは先
送りする、という政策である。その意図は実現した。金融政策により株式市場のミニバ
ブルが起こり、大幅な円安が進行している。意図通りのことが起きた。だから、アベノ
ミクスは成功したのである。唯一の問題は、アベノミクスの成功により日本経済が悪く
なったことである。
・今後の経済は、短期的には、GDP増加率はゼロ付近、あるいは緩やかなマイナス傾向
となると見込まれている。財政支出や消費税先送りにより、一時的にプラス幅が大きく
なる可能性もあるが、その一時的な効果が消えれば、停滞傾向に戻ると見込まれる。実
力である潜在成長率が低いままであるから、そこへ収束することになるだろう。しかし、
これは定常状態だから、悪いことはなく、今後も、失業率は低いままであろう。景気が
悪くなるのではないが、一方、現状よりも良くなることはない。今後、徐々にGDP増
加率は低下していくことになろう。
・このような経済状況においては、アベノミクスで日本経済が良くなることはない。今後、
大都市部の好景気が地方や中小企業に回るということはあり得ない。今、アベノミクス
の恩恵を受けているところ、株高と円安で直接恩恵を受けているところ以外は、マイナ
スの影響が徐々に大きくなるだけだ。
・アベノミクスは、金融政策による株高、円安と、財政政策による短期的なGDP増加率
のかさ上げであるから、それが経済の長期的発展に資することはない。政策により、実
体経済は何も変化していないし、これからもしない。何もしていないのだから、何も起
こらないのは当たり前で、地方経済は、今後もこの2年間とまったく同じ構造であり続
ける。
・何も変わらないのであれば、良くもなっていないが、悪くもなっていないかというと、
そうではなく、確実に悪くなっている。地方が悪くなっている理由は、直接的には、円
安によるコスト高だ。輸入原材料の高騰、電気料金、燃料費、ガソリン代お高騰により、
中小企業は苦しんでいる。輸入業者だけでなく、あらゆる企業、たとえばサービス業で
も同様で、スーパーなども電気代大幅増加でコスト高となっている
・消費者も同様で、ガソリン代、電気代の増加により、そのほかの支出を抑えることにな
る。所得環境は全く変わらないから、コスト増加の分だけ貧しくなる。円安、インフレ
により苦しんでいる。短期的にも、すでに直接の悪影響が広がっている。
・経済というのは基本的に、変動が大きくなればなるほどロスが大きくなる。駆け込み需
要の場合も同じである。駆け込み需要の獲得のために、小売店側は経費をかけて宣伝を
する。それは一度限りしか役に立たない経費であり、時期が過ぎればあとは何も残らな
い。
・消費者の側も同様に一時的な消費となり、後に残らない。駆け込んだ分、お金は使って
しまうし、駆け込むという目的が優先し、それほど必要でないものも買ってしまうこと
になり、後悔することも多い。冷静にお金を使った場合に比べて、幸福度は下がること
になる。売る側も買う側も、祭りのあとは、骨折り損のくたびれ儲け、そして、ロスが
残り、資産が減っているのである。
・アベノミクスの長期的な悪影響は、もっと深刻だ。たとえば、公共事業を地方にばらま
くことによって、今年の雇用を生み出した場合、これは一度限りのものとなる。つくら
れた公民館は、維持費もかかるので無駄であるだけでなく、最悪の場あマイナスの効果
をもたらす可能性がある。さらに重要なのは、今年の雇用は無駄である以上に大きなダ
メージを地方経済に負わせることだ。なせばら、公共事業の仕事は、今年は来たが来年
来るとは限らないからだ。今後10年、20年続くとは思えない。だから、若者は、公
共事業関連の業界に就職しようとは思わない。この仕事を覚えても、長期的に役に立つ
とは思えないからだ。
・多少賃金は低くても、勉強になる仕事に就いていれば、次につながるし、より良い働き
手に成長するだろう。それは、彼らの将来の給料も上げることにもなるし、雇う側にと
っても、より付加価値の高い働き手を手に入れられることになる。これが本当の労使の
好循環だが、この機会を、政策によって奪うことになる。
・公共事業に限らず、一時しのぎの景気対策の仕事をつくることは、長期の成長機会を失
わせることになるのである。個人の働き手としての成長機会を奪い、労使の好循環の成
長機会を奪い、経済全体の成長力も失わせる。三重の成長機会の喪失により、日本経済
全体の長期成長力は大きく低下する。いや、低下させてきたのである。これが、失われ
た15年を生み出したのである。「あの苦しかったデフレの時代」とやらを作り出した
のである。
・アベノミクスの「日本を取り戻す」という政策は、まさにこれだ。1960年代の日本
経済に戻ることを望むような政策は、日本経済の成長機会を喪失させる。日本経済は政
策によって、「新・失われた10年」を迎えるリスクを抱えてしまったのである。
・アベノミクスは、金融政策で一時的な株高をもたらしたが、一方で、実体経済に対して
は何ももたらさなかったのみならず、円安によりコスト高を招き、交易条件を大幅に悪
化させ、日本経済全体を窮乏化させている。将来の経済に対しても、短期の景気刺激を
優先することにより、長期の成長機会を奪い、ただでさえ低い日本の長期成長力の将来
性を低下させている。
黒田バズーカの破壊的誤り
・大規模な超金利緩和は必要ない。なぜなら、失業率は3%台半ばで完全雇用に近い水準
であり、景気は良く、また、銀行危機や金融市場の危機も起きていないからである。極
端な金融緩和は、コストとリスクを伴う。だから、必要がないのにやるのであれば、そ
れは害である。
・黒田総裁は、五つの誤りを侵している。第一の誤りは、円安が日本経済にとって望まし
いと考えていることである。その時代は1980年代前半に終わった。第二の誤りは、
インフレ率を上げて実質金利を下げようという考え方だ。しかし、現在の日本では、こ
の効果はほとんどなく、また、無理にインフレ率を動かさなくても実質金利低下は達成
可能である。
・日本の現状ではインフレ率を上げて実質金利を下げようとするメリットはほとんどない。
理由は二つある。第一に、実際に金利は下げ余地があるからである。インフレに頼らな
くても、金利引き下げは実現可能であるということだ。普通は、短期よりも長期のほう
が金利は高くなっているから、長期金利はプラスであって、これは下がる余地がある。
・量的緩和政策の効果は、実際には、インフレを起こすことではなく、長期国債の買い入
れそのものから生じる、買い入れによる国債の値上がりがすべてだ。つまり、国債の値
上がりとは金利の低下であるから、長期金利の低下が実現するのだ。
・企業は、税制優遇もあって、設備投資をすでに十分おこなっており、金利の多少の低下
で投資を増やすことはなかったのである。それよりも自社の製品に需要があるかどうか、
自社のポジションが世界でどうなっていくかの見通しのほうが重要であり、投資すると
しても海外が中心であった。個人の住宅も、持ち家率が米国よりも高く、収入が十分に
あるほとんどの家計では、すでに住宅を購入していた。したがって、そもそも金融政策
の余地はほとんどなかったのであり、量的緩和の投資促進に対する効果は、気合を見せ
る以外にはほとんど何もなかったのである。
・デフレスパイラスなどというものは存在しない。デフレによる買い控えもない。悲観心
理は存在するが、その原因はデフレという物価水準の下落ではない。将来への悲観論が
すべてで、これが需要を弱くした。この結果として物価が上がらなくなっているのであ
って、物価が原因で悲観論や消費手控えが結果、というのではない。因果関係が逆なの
だ。
・消費者は必要なもの、欲しい物を値下がりするからといって10年も待ち続けることは
ない。せいぜい、バーゲンになったら買おうと衣料品を数ヶ月我慢するだけのことだ。
しかも、このようなバーゲンハンターは、もともと毎年バーゲンでしかかわないのだか
ら、消費の先送りをしているわけでは一切ない。毎年季節はずれのものを買うだけのこ
とだ。テレビなどの家電製品、進捗の早い携帯電話、パソコンなどもそうであるが、型
落ちを待って、次のモデルが出てから買う人は、常にそういう行動をとっているだけの
ことだから、これも消費を先送りしているわけではない。物価の継続的な下落により消
費を先送りしている消費者は存在しない。デフレスパイラスは存在しないのだ。また、
実物投資でもあり得ない。ビジネスチャンスがあるのに、来年のほうが1%安いからと
いって投資を1年待っていたら、この企業はチャンスを逃す。潰れてしまう。
・デフレスパイラルが起こるのは金融市場だ。安く買って高く売るのであるから、安くな
るのであれば、それは絶対に待たなくてはならない。さらに、下落が継続しているなら
ば、その途中で買ってしまっては致命的だ。明らかに損をすることになる。だから、投
資家たちは買いタイミングを待ち続ける。下がると思えば誰も買わないから、実際に下
がる。さらに下落期待が強まる。ますます誰も買わない。さらに下がる。さらに待つ。
まさにデフレスパイラル、いや暴落スパイラルだ。
・デフレスパイラルが先進国で起きたのは、大恐慌の次はリーマンショックだった。あれ
はまさにスパイラルだった。需要がこの世から消え去ったような数量調整だった。危機
である。1998年の日本の金融危機もまさに危機であり、それはデフレなどという生
易しいものではなく、証券会社、銀行の破綻、金融システム危機だった。
・将来の物価の下落が現在の消費を手控えさせたのではなく、将来の所得不安、将来の年
金制度不安、将来の日本の政治への不安、高齢化社会、人口減少、日本は終わりだとい
うような悲観論の蔓延が、消費を萎縮させ、投資を手控えさせたのであり、株式市場は
まさに、自己実現であるから、悲観論が自己実現したのである。
・物価の0.5%の下落を2%のプラスにしたところで、消費が増えるはずはない。プラ
ス1%のインフレ率の予想値を2%にしたところで、消費は動かない。むりろ、物価上
昇率より買えるものが減るから節約に走り、消費は減ることになる。将来の所得上昇が
期待できなくては、消費は増えない。インフレが所得上昇につながるとは誰も思わない。
・しかし、なぜ、インフレが問題なのか?それは、インフレの下では、将来への投資が起
きないからである。インフレになると、将来の価値がどのくらいになるか、わからない。
予測が立てにくい。投資とは現在買って将来売ることであるから、買うほうのコストは
確定するのに、将来の収入は確定しない。それは困る。だから、インフレの下では、将
来への投資が起きないのである。将来の変動の不安により阻害されるのは、設備投資だ
けではない。将来が不安であれば、人々は、消費も控えるし、いろいろな契約、人生の
決断も差し控えるだろう。住宅も購入しない。住宅の購入は、個人にとっては最大の投
資だから、影響は大きい。
・インフレの何がいけないかというと、1000%という水準そのものではなく、何%に
なるかわからない、ということが問題なのだ。インフレ率自体は何%でもよい。諸悪の
根源はリスクがあること、すなわち、将来のインフレ率が確定していないこと、そして、
その変動幅が大きいことだ。逆に言うと、インフレ率が固定していれば、インフレ率の
水準がいくらでもかまわない。
・ここ15年の日本は、インフレ率のコンセンサスの水準が確立していた。これ以上確立
していないぐらい確立しており、ほぼ100%であった。この程度のインフレ率ならば、
誰もインフレ率をまったく気にしなかった。誤差があっても1%からの誤差なら、無視
できるようなものだった。それを黒田総裁は、政策によって、あえて壊そうとしている。
ありとあらゆるコストとリスクをかけて、日本銀行の使命として、壊すことに全力を挙
げているのだ。これ以上、誤った政策はない。ここで重要なのは、現実のインフレ率も
将来のインフレ率への人々の予想も1%で安定しているのに、この状態をあえて壊そう
としていることである。これほど愚かなことはない。
・安定しているものを動かすのだから、極めて不安定な状態に陥る。市場は混乱し、人々
の期待、投資家の思惑は錯綜する。混乱した金融市場は、投機家にとっては絶好の稼ぎ
場、長期投資家にとっては最悪の状況となる。これは一番避けなければならないことだ。
それをあえて行っているのだ。
・黒田総裁の異次元の金融緩和は、中央銀行としては、21世紀最大の失策の一つとも言
える。なせか?まず、原油下落という最大の日本経済へのボーナスの効果を減殺してし
まうからだ。日本経済の最大の問題は、円安などによる交易条件の悪化だ。原油高、資
源高で、資源輸入大国の日本は、輸入に所得の多くを使ってしまい、他のものへの支出
を減らさなければならなくなった。これが今世紀の日本経済の最大の問題だった。
・これに歯止めをかけてくれるのが、原油価格の暴落であり、天の恵と言ってもいいくら
いのものである。それにもかかわらず、わざわざ相殺するように、物価が下がったら困
るという理由で、円ベースの原油価格を引き上げてしまった。インフレを起こすために、
円ベースの原油の輸入価格を押し上げる金融政策をとったのである。これは明らかな間
違いだ。180度間違っている。
・量的緩和とは、現在では、実質的には国債を大量に買い続けることである。これはリス
クを伴う。国債市場がバブルになり、金融市場における長期金利、金融市場のすべての
価格の基盤となっている価格がバブルとなるのであるから、金融市場が機能不全になる。
それを承知で、すなわち、バブル崩壊後の金融市場の崩壊のリスクは覚悟のうえで、国
債を買い続けている。中央銀行が買い続けている限りバブルは崩壊しないので、そのバ
ブルが維持されている間になんとかしよう、という政策である。この場合の最大のリス
クは、財政ファイナンスだとみなされることである。それによって、中央銀行に対する
信頼性、貨幣に対する信任が失われることである。
財政ファイナンスに限らない。貨幣およびその発行体である中央銀行に対する信任が失
われるのであれば、その原因、きっかけは何であれ、中央銀行は危機を迎える。危機と
いうよりも終わり、中央銀行の終焉である。量的緩和は、あえて、自己の信用を失わせ
るような手段をとりつつ、信用を維持することを目指すという綱渡りのような、非常に
危うい政策なのである。
・国債などを大量に買い入れるという、この「量的緩和」は米国も行ってきた。しかし、
「量的緩和」はリスクを伴う危うい政策である。このような危うい政策は、どこかで脱
出しないといけない。米国中央銀行FEDは脱出に成功しつつある。出口に向かい始め
たのだ。しかし、日本は脱出に失敗するだろう。なぜなら、米国FEDとは根本的に考
え方が違うからだ。
・なぜ、米国が成功し、日本が失敗するのか?米国は、インフレターゲットは手段であり
目的ではない、ということをわかっているからだ。彼らは2%のインフレターゲットを
掲げながら、インフレ率が2%に達していなくても、出口に向かい始めた。なぜなら、
目的は米国経済だからだ。日本は、まったく違う。二重の意味で根本的に米国と違う。
第一には、インフレターゲットを最優先していることだ。期待インフレ率を2%にする
ために、原油安というメリット、交易条件の改善というメリットを消してまで、手段を
達成しようとしている。日本経済という目的よりもインフレ率という手段を優先してい
る。
・日銀が米国FEDと致命的に異なっている第二の点は、達成的ない目標を掲げていると
いうことだ。すなわち、「期待インフレ率」という、目標とすべきでない目標を掲げて
いることだ。インフレターゲット最優先よりも、さらに悪い。目標として間違っている
と同時に、達成不可能な目標であるからだ。達成不可能な目標を遮二無二達成しようと
しているから、無理が生じる。そして、達成するまでコミットを続けるのだから、永遠
に間違った政策を続けることになる。そして、この政策は、経済にとって短期的にもマ
イナスであり、長期的には大きなリスクを伴う。マイナスのことを永遠に続けるから、
日本経済は悪くなり続ける。長期的なリスクをとり続けるから、いつか、そのリスクは
必ず実現する。つまり、経済か中央銀行か、どちらかが破綻するまで続けることになる
のだ。「この道しかない」という道は、経済または中央銀行が破綻することが必至であ
る道なのである。
・インフレ率に対しては直接の手段はない。金利や量的緩和という間接的な手段しかない。
インフレ率は経済全体で広く形成されるものだ。だから、インフレターゲットはそもそ
も目標ではなく手段なのだ。ましてや、その予想値である「期待」インフレ率など誰も
コントロールしようとしない。
アベノミクスの根本思想の誤り
・アベノミクスで経済は良くならない。それは、根本的な思想が誤っているからだ。経済
の本質を理解せず、日本に真に必要なことをわかっていないからだ。それは、日本経済
の問題は需要不足ではない、ということだ。
・景気が悪い、というのが経済の問題ではない。景気対策はいらないし、景気は刺激する
必要はない。むしろ、それは無駄であり、経済成長を阻害するものだ。日本の失業率は
低い。3%台半ばである。これは、ほぼ完全雇用に近いと言われている。つまり、需要
は足りているのであり、仕事は足りているのである。むしろ、働き手が足りないのだ。
実際、パートやバイトの時給は大都市では上昇しており、明らかな人手不足だ。だから、
財政支出や減税は不必要である。
・公共事業などは、不必要どころか、害悪である。なせか?第一に、負債が残る。借金を
返さなければならない。不必要なモノが残り、借金が残る。最悪だ。第二に、無駄なだ
けでなく維持管理費がかかるので、無駄以上にロスが発生する。明らかにマイナスのモ
ノが借金とともに残される。第三に、公共事業という仕事が今年限りの単発の仕事で、
持続性がある、未来のある仕事ではないことだ。雇用として最悪の仕事である。第四に、
万が一、仕事に就いてしまったら、最も悪い結末となる。ほかの仕事をする機会を失う。
・現在、政府も、公共事業への批判に応え、かつ、地方を活性化するために、地方に配る
モノを地域振興券、あるいは、プレミアム商品券というようなものに切り替えてきた。
これは、要は、個人への現金バラマキである。しかし、これも100%間違っている。
公共施設などと違って、維持管理費はかからないし、また個人も現金をもらって困るこ
とはないから、公共事業に比べればましではあるが、やはり、マイナスであることは間
違いがない。少なくとも、メリットはまったくない。政府の借金あるいは将来の増税を
財源に現金をばらまいているだけであるから、せいぜいプラスマイナスゼロである。
・消費を刺激することは、現在の日本経済にはマイナスである。景気刺激策と言えば消費
喚起、貯蓄は罪、経済のためには無駄遣いしてもとにかく消費しないといけない、消費
こそが経済のすべて、というような風潮がある。だから消費刺激が経済にマイナスなど
あり得ないと思われるかもしれない。しかし、奇をてらっているわけではない。貯蓄の
しすぎは過剰貯蓄であり、長期の安定的な消費水準は下がる。一方、過剰に消費してし
まうと、貯蓄不足が投資不足をもたらし、資本貯蓄が不十分で、長期の経済成長率が低
下し縮小均衡に陥ることになる。
・実際、アジアの高成長は貯蓄率によるものだというのが未だに定説で、日本がその代表
であり、他の東アジアの国々がそのお手本として取り上げられてきたのである。つまり、
物事には妥当な水準があるということであり、消費も最適が水準にあることがベストで
あり、消費しすぎも、貯蓄しすぎも、どちらも良くない。それだけのことである。ただ、
肝心なのは、今や日本は消費不足ではなく、貯蓄不足だ、ということだ。
・2013年度の家計の貯蓄率は、1955年以降、統計が利用可能になってから初めて
マイナスとなった。日本経済は、全体で貯蓄を取り崩す経済になったのである。日本は
消費不足ではなく貯蓄不足なのだから、さらに消費を増やせば、貯蓄不足はまします深
刻になり、投資不足、資本貯蓄不足となり、経済成長率はさらに低下することになる。
実は、近年の成長率の低下の一因は、消費のしすぎにあるのである。
・消費は今期の需要になるが、それが終わりであって、次につながらない。将来の経済成
長につながらない。将来の経済成長は、投資による資本貯蓄によるのである。投資とは、
経済学的には、貯蓄の裏返しであり、貯蓄とは、所得のうち消費されなかった分である。
だから、貯蓄を増やし、投資を増やし、資本貯蓄を進めるためには、消費は減らさなけ
ればならない消費を増やすことは、経済成長率を低下させるのである。
・消費至上主義という誤りには、関連したもうひとつの根本的な誤りがある。それは好
循環至上主義である。経済は循環だから、無駄遣いでもいいから消費して、おカネが経
済に流れれば、それが誰かの所得になり、その人がまた消費すれば、また誰かの所得に
なり、と循環していく。この好循環を生み出すことが、経済にとって最も重要であり、
経済政策は、これが肝だ。いったん経済がうまく循環し始めれば、永遠に拡大する。こ
れが、持続的な経済成長である、そう思っている人々がいる。これも、根本的な誤謬だ。
消費をせずに貯蓄してしまうと、そこで流れが止まって、経済が止まってしまう、拡大
を止めてしまう、不況になってしまう、と思っている。それは違う。経済はそんな自転
車操業のようなものではない。貯蓄されたおカネは眠りはしない。消費が誰かの所得に
なるように、貯蓄は誰かの投資になるのである。日本経済は完全雇用をほぼ達成し、需
要不足ではない。それでも成長率はゼロであるのは、潜在成長率がゼロ程度だからだ。
潜在成長率とは、供給力の増加率である。すなわち、供給力不足が、日本経済の真の問
題なのである。したがって、消費を政策で刺激することは、意味がないどころか、成長
を阻害するのだ。
・大恐慌など、失業率25%、需要が経済全体で半分に減るというような状況、最近で言
えばリーマンショックのような状況、これらの場合には政策で消費を刺激することは必
要だ。需要を増やして、凍りついた経済を循環させることを政策で行いことに意味はあ
る。しかし、平時、普通の景気循環の中での景気悪化に対しては、危機における財政出
動と同じようなイメージで政策を大盤振る舞いすれば、経済には大きなマイナスになる。
・現状で、需要が足りない、あるいは景気が悪いと感じるようであれば、それは景気循環
ではなく、経済そのものの力が落ちていることから来ている。供給力不足が原因であり、
柔軟で、現在に適した人的資本や設備が足りず、世の中のニーズに合ったモノやサービ
スが生み出せなくなっていることが、成長力低下に原因だ。このとき、消費を刺激すれ
ば、貯蓄が減り、投資が減り、成長力はますます低下する。成長率低下スパイラルに陥
ってしまう。
・供給力不足とは、牛丼チェーンのバイトが足りない、というような量的な問題ではない。
むしろ、量よりも質が重要だ。きちんと店を回せる店長が不足していることが問題なの
だ。日本経済に必要なのは、需要でもなく、単なる物量の供給力でもなく、供給の質、
すなわち、人的投資と実物投資だ。丁寧に人を育て、質の高い設備投資をすることが必
要なのである。
・設備投資を刺激して景気を良くするという戦略は、高度成長期の景気対策としてはベス
トだが、現在の日本経済には当てはまらない。なぜなら、この設備投資による景気対策
戦略とは、設備投資を需要として活かすことに力点があるからだ。つまり、本質的には、
供給力対策ではなく需要の量を増やす対策なので、質の高い供給力が何よりも必要な日
本経済の現状には合わない。
・「成長軌道に戻す」という言葉をアベノミクス推進者は使うが、そもそも21世紀の日
本経済においては、もはや成長軌道は存在しない。
・21世紀の世界は変化が激しく、今年売れるものが来年売れるとは限らず、同時に今期、
有用な設備が来期も有用で効率的とは限らない。今日の設備投資が明日の経済に適合的
でない可能性が高い。量的な不確実性も質的な不確実性も高く、二重の意味で無駄な設
備となり実際のニーズと合わない、単なる過剰設備になってしまう可能性が高いのであ
る。現在の経済は複雑で多様性に富み、変化も激しい。市場も世界に広がり、それは世
界の各地域のローカル特性を持った市場である。力任せに効率よく安いモノとつくれば
売れるわけではない。このようなときに、今日の需要のために、何でもいいからとにか
く設備投資をしておけ、という考え方で設備を増やすと、明日以降の過剰設備、不況の
原因となるのだ。その設備にこだわる企業は、売れないものをつくり続けて赤字を拡大
するし、その設備に熟練した労働者は使えない労働者になってしまう。右上がりの単純
に規模を拡大する経済において成立した設備投資モデルは現在の経済には合わない。
・「貯蓄が投資に回らないのが問題だ、貯蓄から投資へ」というかけ声、あるいは呪文を
よく聞く・所得のうち消費しない分が貯蓄であり、その貯蓄は、経済全体では必ず投資
として使われる。貯蓄=投資なのだ。「貯蓄から投資へ」というかけ声は、銀行預金か
ら株式投資へ、ということに過ぎず、株価つり上げキャンペーンにすぎない。証券会社
が確信犯的に、このかけ声を信奉するのはわかるが、日本人は貯蓄なかりで投資しない
から経済が成長しない、という発言をするエコノミストがいれば、経済がわかっていな
いか、インチキかのどちらかだ。本当の問題は、貯蓄としての銀行預金が有効に活用さ
れているかどうかだ。
・銀行はリスクを取らず、国際ばかり買って無駄に使っている。だから、銀行預金よりも
株式投資を個人がして、資金を有効活用せよ、という議論もあるわけだが、この議論も
適切ではない。政府が国債などを大量発行して借金を1000兆円もしているから、銀
行預金が国債に回らざるを得ないのである。銀行や生命保険会社が国債投資を止めたら、
それこそ、日本の金融市場は崩壊し、経済は危機に陥る。政府が借入れた1000兆円
を意味のある将来への投資に回し、経済の供給力としてくれれば、経済も成長したはず
である。だが、この1000兆円を、政府は、将来へ向けての供給力となる投資に使わ
ず、ほとんどが無駄な政府支出として浪費してしまったり、あるいは年金支出など意味
のあるものだったとしても、要は、消費してしまっているのである。この結果、資本が
日本経済に残っていないのでる。だから、成長できないのだ。
・おカネを借りて、それをまともな資産として蓄積せず、また収益を生む投資もしない。
何も生み出さず、ただ使ってしまったとすれば、借り手には借金しか残らない。返そう
と思っても返すモノがない。政府の場合も、いざ1000兆円返せ、と我々が言ってみ
ても、政府は税金で新たに国民から奪わないことには払えない。
・1000兆円を返す必要がない、という議論もあるが、返す返さないの問題ではない。
その1000兆円を有効に使ったか、経済にプラスをもたらす投資を行ったか、という
ことが重要なのだ。1000兆円を民間投資していれば、高い経済成長が実現できたは
ずだし、海外に投資をして収益をあげれば、対外資産が増大し、将来、所得収支として
日本に還流し、労働力が減少し勤労稼得所得が減少した経済において、貴重な収入源と
なり、消費を支えたであろう。政府の消費、投資、カネの使い方の非効率性は誰もが認
めるところだから、政府に1000兆円貸すよりは、付加価値を生み出し、元本を利子
とともに返してくれる民間経済主体が有効活用するべきだった。1000兆円の消費に
より、日本の経済成長は失われたのである。
・とにかく消費を刺激して、カネをぐるぐる回し、カネ回りを良くして経済を活気づける
という考え方は根本的に間違っている。トリクルダウン、すなわち、お金持ちが無駄に
カネを使えば、庶民も潤う、という議論は誤りである。それは、投資の機会がなくなり、
供給力と成長力が失われることである。国内で投資ができなくなるとしても、海外に投
資をするなどして、現在よりも経済全体の消費が減り、需要不足になると思われる将来
に、必要な資産、食いつぶすだけの資産をとっておいたほうが日本経済においては有益
なこととなる。
・アベノミクスは、根本的な経済のとらえ方、経済政策についての考え方が誤っているの
で、今年の景気を刺激することはできても、持続的な成長をもたらすことは決してでき
ない。それどころか、成長機会を殺しているのであり、中長期的には経済の活力が失わ
れていくことになる。
日本経済の真の問題
・この20年間の低迷は、日本経済の低迷ではない。日本の経済政策の低迷だったのだ。
失われていた「政策ヴィジョンの構造改革」。これが、今、必要なことである。マクロ
経済政策偏重からの脱却、景気対策からの脱却、国全体での成長戦略からの脱却である。
デフレ脱却は重要ではない。
・景気が悪いのではない。景気循環は順調だ。過熱しているくらいだ。だから、景気刺激策
はまったく必要ない。それどころか、マイナスの影響がある。日本経済に必要な成長力
を奪うからだ。
・景気が悪いのではなく、潜在成長力という日本経済の実力が落ちているのだ。これを回
復するためには、短期的な景気刺激策をとることは無駄であるだけでなく、害なのだ。
・景気刺激策は、既存の経済構造を固定することになり、新しい経済構造の誕生、経済自
体が自律的に持つ柔軟な環境変化対応能力を阻害することになる。つまり、景気対策と
は、ある種の既得権益を守ることなのだ。
・景気刺激策により景気が少し良くなり、見せかけの安息を得て、そこで経済の変化への
対応を止めてしまう。環境変化への対応を止め、同じやり方にとどまり安心し、思考停
止になる。頑張らないわけではない。むしろ、思考停止して、これまでと同じ場所で、
同じことをひたすら繰り返し、環境には目をつぶって、遮二無二、死ぬほど努力する。
それは、本当にもったいない。頑張るなら、未来のある努力のほうが誰にとっても望ま
しい。政策サイドもこれに応えようとし、ひたすら景気対策が繰り返される。そして、
効率の悪い場所にとどまったまま、全力で努力しながら、過労死を迎えることになる。
それではだめなのだ。
・必要なのは、政策に頼らない経済と、政策に頼らない人々の姿勢をつくるための政策で
ある。そのためには、景気対策は止める必要がある。景気循環への対応は、金融政策に
よる微調整に限定する必要がある。
・では、何をするのか?成長力を上げること、長期的な日本経済の実力をつけることだ。
しかし、それは量的な拡大ではない。まず、GDP増加率を成長の指標として使うこと
を止めることが必要だ。
・GDPの増大は成長ではない。単なる膨張だ。人口が増えれば自然に増える。人口増加
は経済のためではなく、社会のためである。社会としての必要性の有無を考えるべきだ。
低賃金労働力の不足による経済規模の縮小を防止するために、移民を促進するというの
は、経済規模だけを考える誤った政策である。社会として、移民に関する望ましい形を
先に考えるべきである。多様な国籍の人々が集まることが良い社会であるといいことと、
経済規模を維持するために、低賃金労働力のプールとして移民を促すこととは、まった
く別の問題だ。
・少なくとも経済成長は、経済全体のGDP規模で考えるのではなく、一人当たり国民所
得で考えるべきである。そうすると、ただ経済の規模を大きくするのではだめで、経済
の効率性を高め、経済の高度化を図ることが必要となる。量より質となり、真の意味で
経済の成長を目指すことになる。
・しかし、本当は、一人当たり国民所得で考えることも適切ではない。なぜなら、一人当
たりになったとはいえ、依然として、国民所得という「量」で考えていて、質を考えて
いないからである。つまり、一人当たり国民所得とは、所得水準という金額で測った水
準あり、本当の意味での経済の成熟度を測っているわけではない。真の豊かな生活を表
しているわけではないからだ。
・日本の一人当たり国民所得を上げるためには、都道府県別一人当たり県民所得がダント
ツに高い東京を、全国で見習えばいいのか?明らかにそうではない。国土が全部東京に
なれば、日本中の生活コスト、社会コストが東京並みに上がるということだ。とんでも
なく住みにくい国になってしまう。あらゆる活動が、金銭的尺度あるいは価値で測られ
る大都市に比べ、普通の街、市町村では、金銭に表れない豊かさがある。東京などの大
都市での生活は、この豊かさを犠牲にして、その分、しかたなく、高い給与を得てごま
かしているのだ。
・実は、日本でも、20代の子供のいる夫婦に多いのだが、東京を避けて、環境の豊かな
地方に移住することを望む人が増えており、少しずつ実現もしてきている。これは、住
環境、子育て、教育環境を考えれば、当然の結果とも言える。生活環境お豊かさは計り
知れない。コンビニがなくて困る、のではなく、コンビニで食事をすまさずにすむ、の
である。食生活は質的に次元が違う。コストも圧倒的に低い。住環境も、違いすぎて比
べようがないが、東京で木を見つけて喜ぶのとは異次元である。自然を探すのではなく、
自然の中に住んでいるのだから、当然だ。まさに異次元である。公園も庭もいらない。
自然がすべてを提供してくれる。
・指標が手に入るGDPを手頃な目標として設定してはいけない。成熟経済の指標がなの
であれば、正確ではなくとも可能な範囲で指標をつくるか、それが難しければ数量的な
指標なしに進んでいくしかない。
・まず失業率の低下への対策が優先される。仕事がある。これが何よりも重要である。失
業はなんとしても避けるべきものだ。賃金水準も重要だが、それも失業の関連としてと
らえるべきだ。たとえば、見かけの失業率は低いが、多くの人が労働条件に関して不本
意であり、とりわけ賃金水準についての不満が広がっているのとすれば、実質的な雇用
問題は、見かけの失業率を超えて、根深く大きな問題となっていると、とらえる。潜在
的な失業とも考えられる。だから、失業の減少、幅広くとらえれば、雇用が最大の目標
となる。
・「質的な豊かさ」はどのように追求するのか。「成熟社会」をどのように追求するの
か。すべては各個人と各地域である。個人の成熟と地域社会の成熟が基盤となって、日
本経済全体の健全な成熟が実現するのである。経済は、個人の総和である。日本は、各
地域の総和である。したがって、これら個々の力を高めることを支える役割を政府は果
たすことに集中する。これが、唯一の長期的経済成長戦略であり、我々の言葉で言えば、
成熟経済のヴィジョンである。
・成熟社会においては、個人の価値観、各地域のあり方は、多様になる。だから、マクロ
経済政策を日本全体に押し付けることは意味がない。マクロ経済政策は環境整備に尽き
る。安定した経済環境を維持することに尽きる。安定した物価、為替、金利。それで十
分だ。
・成熟経済においては、日本全体の経済を動かすマクロ経済政策は脇役になる。それと同
時に、トップダウンの手法は通用しなくなる。国レベルでヴィジョンを決め、日本全体
がそれに向かって突き進む、というスタイルは高度成長期までだ。それぞれの地域は、
それぞれの道を歩むから、国全体での方針、計画はいらない。邪魔である。
・この20年間の低迷は、日本経済の低迷ではなく、日本の経済政策の低迷だったのだ。
経済政策は何のヴィジョンも思想もないまま、焼け石に水のような景気対策だけを繰り
返し、借金を急増させていった。日本の資産である貴重な金融資産は、成長を生み出さ
ない政府の財政支出に注ぎ込まれた。その結果、もともと低成長化が進んでいた日本経
済の成長力をさらに低下させた。その中でデフレマインドと呼ばれるものが生まれた。
・デフレマインドとは、将来の物価下落に対する不安ではなく、将来の所得、雇用環境へ
の不安であった。この結果、消費は抑制され、将来の社会保障への不安から、高齢者は
必要以上の貯蓄に走った。将来所得、将来雇用の不安は、将来の政府への不安、政策へ
の不安、不信により、増殖していった。一方、政策サイドは、この不安から生じる経済
の停滞に対し、景気対策という、一見、その場しのぎ、実はその場しのぎにもなってい
ない、無関係なもので応じた。これが、ますます政府不信、経済政策不信を増長させた。
将来への悲観マインドは高まった。
・金融危機からの回復には成功したが、副作用として、金融危機脱却後、円安、株高が何
よりも必要であると信じ、その実現を政府の政策に依存するという、堕落した体質とな
ってしまった。経済政策の思想としても「日本経済は需要不足であり、景気を刺激し、
消費を促すことが何よりも必要である」という1960年代の思想から一歩も変化でき
なかった。古い景気対策を継承し、さらに拡大して、繰り返し行うこととなった。堕落
しただけでなく、堕落する方向も180度誤っていたのである。この結果、日本経済の
潜在成長力は大幅に低下した。政府はこれに対し、経済政策の思想も構造も変えずに、
さらなる景気対策で応じた。結果的に、景気対策の規模は大きくなり、借金の額の増加
速度は加速し、金融政策に至っては、極めてリスクが高く、根本的に誤った考え方の異
次元緩和が行われることになってしまった。
アベノミクスの代案を提示しよう
・アベノミクスとはなにか?それは、「超緩和的金融政策」である。それによる、株高と
円安、国債市場の混乱だ。そこからいかに少ないリスクとコストで、途中下車するか?
この危機から脱出する方法はあるのか?
・アベノミクスとは「超緩和的金融政策」である。結局これに尽きる。超緩和的金融政策
で何が起きたか?株高と円安、および国債市場の混乱である。要は、日銀が国債市場に
介入し、その結果、活が上がって円が下がったのである。
・円安は、日本経済全体にマイナスの影響をもたらした。原油をはじめとする輸入品を高
い価格で輸入せざるを得なくなり、交易条件が悪化したからである。これは格差の問題
ではない。大企業が輸出で儲け、富裕層が株で儲け、低所得者がガソリン、食料の必需
品の値上がりで苦しみ、中小企業の大半が内需企業で、原材料費や光熱費などにおいて
円安による輸入品のコスト上昇で苦しくなった。しかし、この格差が問題なのではなく、
経済全体トータルで損をしていることが問題なのである。
・自国の通貨が安くなると、その国の経済は損失を被ることになる。交易条件の悪化によ
り所得が流出し、国全体の経済厚生は低下することが知られている。交易条件の悪化と
は、同じ原油をより高い値段で買わされることで、貿易を物々交換と考えれば、同じ量
の原油を買うために、これまでは車を1台外国に渡していたものを、今後は2台渡さな
ければいけなくなる。同量の原油は買わないといけないのでそれ以外のモノへの支出を
減らすことになり、実質的な可処分所得が減り、貧しくなる。円安誘導は、意図的に日
本経済の世界に占める割合を低下させる。国民一人一人にも大きな影響がある。
・1600兆円の個人金融資産は、20兆ドルから13兆ドルに激減した。日本経済の規
模は、フローで見てもストックで見ても、4割減少したのである。4割の国富が失われ
たに等しいのだ。これまで努力して積み重ねてきたものが、意図的に40%目減りさせ
られたのである。国富が意図的な経済政策により吹き飛んてしまった。戦後70年の努
力が意図的に消されてしまったのである。
・やるべきことは、円安を止めること。国債市場を崩壊させないこと。財政ファイナンス
から脱却すること。量的緩和を止めることは、インパクトが大きすぎて、できない。量
的緩和お開始時点なら、量的緩和を止めるという選択肢はあり得るが、量的緩和が、異
次元、超緩和状態になってしまってからでは、直ちに止めることは不可能だ。もう遅い。
崖の上で綱渡りを始めてしまった以上、綱渡りを止めることはできない。なんとか向こ
う側にたどり着くか、より困難であるが、慎重に後ずさりして戻ってくるかしかない。
止めることは、飛び降りることである。
・超金融緩和状態が進んでいる現在でもベストシナリオは何か?金融緩和は続け、ゼロ金
利は維持するが円安を志向しないことを示すことだ。そのために、まず、量的緩和の規
模の拡大はこれ以上はしない。経済に変化があれば、あらゆる金融緩和は行うが、国債
の買い入れ増額はしない。
・もはや、異次元緩和を織り込んで、国債市場、株式市場、為替市場は動いている。バブ
ル的な側面もある。ここで、最終ゴールとして望ましいからといって、一気に異次元の
超緩和を終了するのは望ましくない。これまでの異次元緩和を直接否定するのもよくな
い。これまで大盤振る舞いをしてしまったツケを払うことになるが、負けないように守
りきる金融政策を行う。異次元の緩和、量的・質的緩和から、普通の大幅な金融緩和に
まず移行し、その後、大幅な金融緩和は幅の縮小を恐る恐る行うのだ。
・市場は、もちろん、これを見透かすだろう。このような金融政策へ移行すれば、当初は、
株式市場は暴落し、為替は円高に振れ、国債市場も暴落するだろう。しかし、ここで守
るべきは、国債市場だけだ。株式市場は思惑の値付けが消失するだけだ。バブルだから
しかたがない。バブルはいつか崩壊する。為替は円高になる分にはかまわない。円が暴
落するのは日本経済の死だが、投機家の思惑が外れて円安が修正されるのであれば、そ
れはむしろ歓迎だ。円高、通貨高は国益、経済にとってプラスであるから、慌てること
はない。乱高下は本来避けたいが、これまで、乱暴に急落してきたのだから、ある程度
やむを得ない。
・問題は国債市場だ。日銀の買い支えを縮小する方向を見透かされるから、一気に暴落す
るだろう。これには、二つの基本方針で臨まないといけない。第一には、過度の下落に
は、買い入れで対応するということだ。国債市場が混乱し暴落するときに、それを買い
支えるのは、金融システムの維持という中央銀行の政策目的そのものに合致する。
・第二の方針は、政府の財政の健全性を示すことだ。消費税率引き上げの延期がきっかけ
で国債の暴落が始まる可能性があり、それが一番恐るべきシナリオだ。投資家の、日銀
買い支えによる国債価格バブルの思惑が崩壊したのではなく、財政リスクが意識されて
の暴落では手の打ちようがない。これを防止するためには、消費税率は引き上げたほう
がいいが、いずれにせよ国債発行額をとにかく減らすことが重要だ。増税延期でもかま
わないが、その場合は、歳出を毎年5兆円カットする必要がある。
・アベノミクスの代案とは、異次元緩和からの慎重な途中下車なのである。あるいは、ブ
レーキが効かなくなった自動車を少しずつ物理的な摩擦を利用しながら、いろいろな障
害物に衝突しないようにハンドル操作をしながら、ブレーキなしで、自然に減速するよ
うにナビゲートする、という感じだ。
・薬物依存ならぬ、量的緩和依存からうまく抜け出すには、苦しみもリスクも伴うが、そ
れを避けていては必ず破綻するので、敗戦処理を忍耐強くやるしかないのだ。だからと
いって、ショック療法はできない。もう薬物依存になってしまったものを突然何の準備
もなしに薬物を抜いたらたいへんなことになる。すべての道には痛みがある。痛みのな
い道は破綻への道だ。
真の成長戦略
・アベノミクスが取り違えているのは、日本は需要不足ではないということだ。景気対策
は一切いらない。景気の波を均すことは、パイを拡大することにはならない。今日膨ら
んだ分のツケを将来払うだけだ。財政出動した分は増税になるのだから、何も増えない。
消費税増税を延期しても、あとで上げるのであれば、上げる幅が長期的には大きくなる
だけのことだから、単なる先送りだ。
・金融緩和と財政出動をセットで行えば、さらに問題は悪化し、財政ファイナンスと思わ
れ、国債市場のリスクがさらに高まる。同時に、政治が中央銀行い国債の処理を短期的
に依存し、易きに流れ、放漫財政が助長される。国債市場破綻リスクがさらに高まる。
他方、政策による経済成長力の低下も起きている。短期の景気刺激を行い、目先の需要
と仕事を増やすと、長期的な活力と仕事が減少する。失われた15年、デフレに苦しん
だ15年と言っていることの根本的な要因は、目先の景気刺激策をやりすぎたことであ
る。景気対策依存症になってしまったことにある。
・量的緩和依存症も同様の現象だが、金融政策は、よりスピード感があり、破壊力もある
ため、リスクも極めて高い。金融市場が相手だけに、変更できる選択肢が限られる。コ
ントロールが難しい。だから、金融緩和によるリフレ政策が最も危険な政策であり、脱
出も最も難しい政策だ。
・まず、景気対策を止める。公共事業はもちろん止める。歳出削減をさらに進める。社会
保障も削減する。その代わり、現状の社会保障を維持するなら30%以上とも言われる
消費税率の引き上げを15%までに抑える。歳出を削減し、歳入もそれに見合ったもの
にする。小さな政府というよりは、「効率的な政府」を目指す。これが、最大の成長戦
略であり、日本の成長力は上げる。なぜ成長力が上がるのか?国債市場を縮小すること
になるからである。つまり、過去15年の政府債務の急増によって、民間にあふれる資
金が政府部門という成長を生み出さないところに吸収されてしまい、いわばブラックホ
ールに吸い込まれたように、資金が成長にまったく貢献しなくなっていることが、成長
率が低下していた根本原因だからである。
・多くの人は、消費をとにかく刺激しないといけない、貯金を取り崩させ、消費させて景
気を良くしないといけない、という誤謬に陥っている。とんでもない。今、この金融資
産を消費してしまったら、将来、使うカネがなくなる。今の経済よりもはるかに縮小し
た20年後の経済は消費したくてもカネがなくなってしまっているはずだ。そのときま
でに消費の原資ををつくっておく必要がある。そのために、消費したくないものを無理
に消費するのではなく、投資する。日本に投資先がなければ、海外に投資すればいい、
需要依存の人々はそれでは需要にならないというが、所得にはなる。きちんと投資すれ
ば、所得になり、国民所得は増える。これが一番重要だ。パイを増やしたいなら、無駄
遣いをするのではなく、賢く投資を稼ぐ。
・将来我々は所得の低下に苦しむ。そのときこそ、資産を食いつぶすのだ。今ではない。
銀行に預けていてはカネが死んでいる、と言うが、それは間違いだ。銀行が国債で保有
しているから死んでいるだけのことだ。国内に融資ができなければ、海外に投資する。
それだけおことでカネは生きてくる。貯蓄から投資へ、ということを言う人は経済をわ
かっていない。貯蓄は投資資金だから、貯蓄がなければ、投資は生まれない。貯蓄の裏
が投資なのだ。消費してしまったら投資は減る。
・銀行が国債を買わず、有効な資金運用をすれば、それは投資として生きてくる。だから
成長戦略は、国債を減らし、資金を活かすことなのだ。これにより、成長が生まれる。
将来の消費の資金が残る。
・日本に必要なのは、貯蓄より投資ではなく、消費より投資だ。消費が足りないのではな
く、投資戦略が足りないのだ。資金をうまく活用できないのが問題なのだ。そして、資
金の投資効率を最も落としているのが、国債だ。政府の借金だ。何も生まずに、何も残
さずに、ただ消費して、資金を食いつぶしている。
・日本経済の実力を本質的に上げる戦略、底力を上げる政策。それは人を育てることだ。
人が成長する。その総体である経済も成長する。何の種も仕掛けもないが、これ以外に
道はない。この道しかない。
・人間が成長するには、10年20年かかるだろう。経済的に個々人が成長するのは、努
力と工夫で、時間はかかるが、地道にやれば必ず達成できる。人を育てるための人を育
てる。それを実現するための人が必要だ。
・今後、我々の多くは、20歳戦後から70歳以上まで働くことになる。就社というよう
なことでは、50年はもたない。50年の間に必ず、会社も環境も変わる。また、職人
でないサラリーマンとしては、1ヵ所で50年はもたない。
・会社の中ではなく自分の中に資本を蓄積する。仕事の経験を人的資本として自分の中に
蓄え、それを活かし、自分でキャリアを形成していかなければならない。個を強くしな
くては始まらないのだ。企業という箱を強くしても、その箱にぶら下がる人々が増える
だけでは意味がない。個を鍛えることがすべての根本だ。
・金融資本の活用により、企業、産業の新陳代謝を進め、政府依存の経済を脱却する。も
ともと日本は、国際的に見て、米国などに次いで、政府依存度が低い民間活力にあふれ
た国なのだ。だから、今までの景気対策依存という誤謬、悪い癖、発想から脱却すれば、
十分道は開ける。政府依存という道は、行き止まりの道だ。
・人口問題は、直接アプローチしない。良い社会は、自然は社会へと立て直していけば、
人口は、結果として自然に増えていくだろう。結婚が遅れたり、出産が遅れたりするの
は、大都市の大企業サラリーマン、サラリーウーマンという働き方の形態に依存してい
ることによる影響が大きい。
・大都市と地方を比べると、物価水準が低いだけでなく、質としても、地方の生活のほう
が圧倒的に豊かであることは、多くの若者が知っている。中高年層ももちろん、そうい
う考え方の人が増えてきた。子育て世代が最も感度が高い。彼らこそ、生活における質
の豊かさを必要としているから、それも当然だ。足りないものは、仕事と学校と病院だ。
ここが政策で補助すべき領域である。学校と病院は、直接、政府の出番があるが、仕事
は、なかなか政府が直接生み出せるものではない。国は、生活コストを低くするという
環境整備に集中すればよい。ある程度人が地方に戻ってくれば、質が高く、質の割には
コストが安い働き手がいる社会になる。ネット通販で味のある企業は、ほとんどが東京
以外の企業だ。日本の地方は、本質的に豊かな地域が多い。
・東京よりも低コストであることは、働き手にとっても魅力だ。給与水準が下がっても、
より豊かに暮らせるからだ。そうなると、サービスの採算も合うようになる。みんなが
東京と同じ所得と生活スタイルとるような錯覚に陥っているから、中央政府の政策は根
本的に誤るのだ。
・地方に住んでも東京に住んでも変わらないものはある。それは輸入品の価格である。地
方だから安くなることはない。だから、円高は必須条件である。地方では、車が重要で
ガソリン価格の上昇の生活への影響が大きいことは有名だが、ガソリンや電気代だけで
なく、多くのものが今や輸入品であり、地方でもそれは変わらない。東京ではユニクロ
はびっくりするほど安いかもしれないが、地方では、まあまあ安いか普通なのだ。だか
ら、生活コストの低い地方を活かすためには、円高は必要なのだ。
・この道しかない、などと、政府のつくった道、短期の甘い痛み止めに依存することから
脱却し、自分たちで道を切り拓くのだ。そのために、政府にはどいてもらう。代わりに
政府がやることはただ一つ。長期的な成長力の底上げに貢献する。そのためには、人を
育てるしかない。政府は、個を育てることに注力する。その補助に注力するのだ。
・人的投資は、必ず日本のためになる。日本の労働力の質を上げれば、多くの企業が、日
本企業も海外企業も日本を拠点にしたいと思う。日本人が日本で教育を受けて優秀にな
って、海外に赴任した場合でも、日本へ彼らの所得の移転が行われることになる。ある
いは、海外に移住するとしても、海外で日本人の評価が高くなることもあり、また、彼
らは、一般には、日本のやり方を何らかの形で海外に広めることになり、優秀な日本人
が海外に散らばっているというのは、ものすごく強いネットワークとなる。
円高・デフレが日本を救う
・今、日本に一番必要なのは、円高だ。自国の通貨の価値を高める。これが、一国経済に
おいて最も重要なことだ。通貨価値とは交易条件の基礎であり、交易条件が改善するこ
とは、一国経済の厚生水準を高める。つまり、国が豊かになる。
・中国としては、通貨が割安であったことは、世界の生産工場として、グローバル生産を
支配するのに役立ったが、それ以上に重要だったのは、通貨が今後強くなっていくとい
うことがコンセンサスであったことだ。つまり、中国に投資すれば、通貨が強くなるか
ら必ず儲かると世界中の投資家に思わせたことである。
・中国に限らず、どの新興国にとっても、通貨は世界規模で輸出先を獲得するための手段
であるから安いほうが望ましいと思うのは一部の輸出業者だけであり、国力の増大にと
っては、通貨を弱くすることは考えられなかった。通貨が弱くなるということは、世界
の投資家が資金を引き揚げるということを意味した。グローバル資本主義により、どの
新興国でも、世界からの投資に依存していたから、長期的に資本を引きつけることは最
優先だった。だから、通貨は強くなる必要があり、そのためにはインフレは敵だった。
また、通貨が弱いままでは、国内の人材、企業、土地などを買い漁られてしまうので、
投資を引きつけつつ、高く売ることが必要で、そのためにも通貨は強いほうが当然望ま
しい。
・先進国は、世界規模に広がった高成長の果実をどれだけ享受できるか、という競争にな
った。それには、通貨価値は高いほうがいい。新興国を中心とする世界経済の拡大の果
実を効率よく刈り取ることが望ましい。そのためには、投資を拡大しないといけない。
果実のなる樹木に、土壌に投資しないといけない。グローバル資本主義の世界とは、資
本を世界に効率よく投資して、その収益を最大化する競争であるから、通貨は力であり、
強くなければ世界に投資できない。通貨価値が倍になれば、倍額の投資ができるのであ
る。
・量を追うことはあり得ない。コスト競争なら、新興国、あるいは新興国になろうとして
いる途上国の中の最も効率が良く質の高い生産力を持つ国に必ず負けるからである。
それらの国は、中国、ベトナム、カンボジア、ラオスと推移してきた。中国はもはや価
格競争は卒業し、付加価値競争に入ってきたのである。通貨を弱くすることにより、あ
えて、自国の価値を低めて貧しくなってまで、この価格競争に参戦する国は普通はいな
い。
・21世紀の現在の成熟国において、ストックである資産価格についても、将来へ向けて
の投資についても、そして、フローの輸出に関しても、すべての軸において、通貨は強
いほうが望ましい。通貨の安売り戦略は理論的にもあり得ないし、現在の日本以外に、
それを望む成熟国はないのである。現代における経済成熟国の最適戦略は、通貨高によ
る資産価値増大およびそれを背景とする新興国など世界への投資である。それにより、
さらに自国の資産を増大させ、さらなるシナジーなどを加え、資産価値を通貨価値の上
昇以上に増大させることを目指す。
・日本の国富(負債を除いた賞味資産)は、2012年度末で3000兆円ある。これを
1ドル80円で換算すると、37.5兆ドルだ。1ドル120円なら、25兆ドル。
33%の減少だ。3分の1が失われたのである。そんな経済的損失は、これまでに経験
ことがない。12.5兆ドルの損失とは数百年分の損失である。
12.5兆ドルを失ったわけであるが、これを世界の金融市場での投資や世界の実物に
投資していれば、少なめに見積もって利回り2%が得られたとしても、0.25兆ドル
が毎年得られるから、100年では25兆ドル、300年では75兆ドル。円安貿易に
よって稼ぐ力の6倍上のペースで資産が増加していくわけであるから、永遠に追いつか
ないどころか、差は年を追うごとに永遠に広がっていく。現実には、国富を直ちに海外
の金融資産に投資できるわけではないから、話はそう簡単ではないが、しかし、経済的
に起きていることは、この数字がまさに表している。一瞬で、この2年で、これまで積
み上げてきた日本の富の3分の1を吹き飛ばし、永遠に取り戻せない損失が生じたので
ある。
・円安に戻して輸出の市場を制覇するというのは、1960年代、あるいは1980年代
前半の日本経済の勝ちパターンに戻りたいということだ。それは不可能であるというよ
り、望ましくなく、圧倒的に不利な戦略である。なぜなら、あえて円安にするわけであ
るから、輸入に極めて振りになるからである。その分を上回る輸出量だけでなく、利益
を稼がないといけない。しかし、円安が進むことによって、貿易赤字は増えている。こ
れは、まさに円安が日本経済にとって、所得のる流出であり、日本経済が貧しくなって
いることを示している。
・この円安が定着、あるいはさらに進行すれば、企業が国内に工場を戻すようになり、そ
うなれば、もう一度輸出が増える、という話がある。しかし、これは幻想であり、同時
に、最悪のシナリオである。海外に工場を移したものを国内に戻すということは、価格
だけで立地を変えているということだ。もう一度円高になれば、ひとたまりもなく工場
は閉鎖に追い込まれ、また海外のコストの安い立地を血眼になって探すことになる。こ
れでは、実は海外生産もままならない。なぜなら、最安値の立地は数年で必ず変化する
からだ。
・質の良い労働力が安く手に入る地域で生産しているということは、その地域の労働力お
よび経済が素晴らしいことを意味するから、必ず経済成長が起こる。日本のほかの企業
も、いや世界中の企業が殺到するから、人件費は急騰する。よって、瞬く間にコストの
優位性は失われる。だから、そのような工場は、中国、ベトナム、カンボジア、ラオス、
ミャンマーと数年ごとに絶えず移っていかなければ、コスト優位性を維持できないので
ある。
・かつて、日本の地方では、雇用を地元に生み出そうと、大企業製造業の工場を誘致する
ことが流行った。しかし、多くの工場は、設立して5年もすれば、設備は物理的には古
くならないものの、世界経済の構造変化、技術進歩、ニーズの変化などにより、経済的
には陳腐化し、企業はほどなく撤退を決意することになった。義理堅く工場を守ろうと
すれば、企業自体が倒れてしまうか、少なくとも製品の生産ラインは維持できず、海外
ライバルに工場を叩き売ることになってしまう。為替レートの変動で工場をかえるとい
うことを想定しているような企業や産業は危ないのである。
・今回の円安は、国富の3分の1が2年で吹き飛ぶような、しかも、それを政策で意図的
に行うという前代未聞、人類史上初めてのことであるから、今までの常識は通用しない、
という見方もあるかもしれない。しかし、だからこそ、立地を変更してはいけないので
ある。金融政策の変更、異次元の異常な金融政策によるものであるから、もし、金融政
策がもう一度変更されて元の方向に行けば、あっという間に為替の流れも変わることが
予想される。しかも、今の金融政策は、明らかに異状であって、日銀自身が異次元と呼
んでいるのだから、必ず正常化が起こる。実際、米国でも正常化が進んでいるのであり、
日本でもいつか必ず起こるのである。
・多くの企業は、工場立地に関しては、この円安が定着するかどうか見極めたいと様子見
をしているところがほとんどだ。それをデフレマインドと呼ぶのは自由だが、為替が安
定するまでは動けないのが常識的な反応だ。異次元の緩和で円安になっているなら、今
の円安のほうが例外的であり、金融政策が将来正常化すれば、今の水準は続かないと考
える企業経営者のほうが、これをデフレマインドと呼ぶ人々よりも、普通だろう。
・フローの衰退は人々の生活を毎日悪化させていくが、目に見えにくいストックの消滅は
さらに致命的だ。1ドル75円が120円になれば、日本経済の規模はドルベースで約
40%減少するので、欧米から見れば、中国に比べ日本はますますちっぽけな市場とな
り、世界で軽視されるようになる。そして、日本の企業も不動産も人材も、40%割安
になり、アジアの投資家が不動産、都心の一等地のマンション、美しいスキーリゾート、
温泉、水資源、しかも、最も価格の高い、最もいいものが買い漁られる。我々は、国富
を、国の宝を失っていく。
・こうして、規模が40%縮小し、世界でのウエイトがほぼ半分と小さくなった日本経済
は、規模の縮小をきっかけに、人災が流失し、活力を失っていく。重要なのは、規模そ
のものではない。規模の縮小により、不動産と同じように、最も優れた企業、最も優れ
た人材が日本経済から出て行く。これこそ、日本の終わりだ。人口減少で日本経済が衰
退する前に、金融政策により40%日本経済は小さくさせられてしまったのだ。
・円高、物価安定によりコストを低くし、世界で最も生活しやすい国とする。円高により、
海外の資源を安く買い、物価の安定により、生活コストを抑え、生産コスト、生活コス
ト、の低い日本にする。通貨が強くなることによって、世界中の素晴らしいモノも企業
も人材も安く手に入る。日本での生活が豊かになり、企業の本社ベースとして、最も優
れた基地となる。日本は世界で最も豊かな拠点となり、社会となる。円高を武器に、こ
のような日本を目指すのである。
・まずは円安を止める。次に、通貨価値を少しずつ回復していく。高い価値を持ったノウ
ハウ、労働力、知的財産を安売りするのを止め、高い付加価値をもたらすものに生産を
特化していく。自国生産にこだわらず、日本でも海外でも生産する。海外労働力、海外
工場をうまく使い、その生産から得られる利益の大半を知的財産による所得、あるいは
投資所得、あるいは本社としての利益として獲得し、国内へ所得として還流させる。
世界経済の変化に企業が対応してきたのを政策で妨害するのを止め、補助する政策に切
り替える。
・この方向が進むと、国内生産量、工場労働者数は減る。しかし、生産量や国内工場雇用
者数をとにかく増やそうとすることは、世界最低コストの労働力と永遠に競うことを意
味する。中国の賃金に合わせ、中国の賃金が上がれば、それより低いベトナムの賃金に
合わせ、ベトナムが上昇してしまえばカンボジアの賃金に合わせる。それで工場で働き
続けることはできるが、世界最低水準の賃金に自ら好んで合わせていくということであ
る。これこそ、デフレマインド、デフレビジネスモデルである。そうではなく、価格の
安い海外の労働力の協力を得て、日本企業の素晴らしい製品を、アイデアの詰まった製
品を、世界最低コストでつくり、世界中に高い価格で売るモデルにシフトする。
・グローバル化、インターネット化した市場では、いわゆるファットテイル、つまり、個
性のあるテイストを持った消費者は、各地域の消費者数は少なくとも、足し上げていけ
ば、世界全体ではかなりの数になる。テイストに合ったモノであれば、その付加価値を
フルに評価して、高い価格でも買う可能性が高い。ある種のオタク、マニアな消費者、
世界中にいるこのような消費者にアプローチできるのだ。これは、日本を開発拠点とす
る大きな理由である。製品開発と基礎研究と連動させて、研究開発を日本で行ってきた
のは、日本の消費者のレベルが世界一高いからである。だから、日本で成功すれば、世
界で成功する可能性は十分にあるのだ。しかし、近年、このモデルの失敗が目立つのは、
テレビメーカーをはじめとする一部の企業が、このビジネスモデルの本質を誤解してい
るかである。世界一の市場で売れたものであれば、世界中に売れるから、そのままグ
ローバルシェアを独占できるという安直な考えで、闇雲に単位当たりのコストを下げた
ために、大量生産のための大規模な設備投資を日本で行ったのが致命的な誤りだった。
核となる製品、能力、ノウハウはもちろん通用するが、各地域はそれぞれローカルだか
ら、そのローカルの需要に合わせていかないといけない。そこを誤解し、世界一の品質
という奢りがあり、失敗したのだ。
・謙虚に、しかし貧欲に世界中で利益を大規模に上げようと思えば、工場は世界で一番安
く、質も十分なところに立地すべきだ。日本に固執するのは、チャンスを失うだけで、
日本生産へのこだわりという自己陶酔をしているだけである。さらに、製品開発は日本
で日本人が、ということにこだわる理由はなく、日本人が優れていれば核としつつも、
世界中の多様で豊富な人材を使ったほうが、さらに大きく成功する。
・最も重要なのは、日本や日本の人々が核になるということである。そのためには、日本
という場を育て、それを支える日本の人々の能力を高めることが最重要だ。場も人で成
り立っているから、すべては、人材を育てることにある。日本の人材が中心になり、海
外の工場の立ち上げも、現地の工場の指導も核になって行う。現地の製品開発の核にも
なる。この人材の価値は非常に高いから、あがった収益や利益はこの人材に帰する。本
社の投資利益とこの人材の所得として、日本経済の収益となる。世界で大きく稼ぎ、利
益は日本のものとなるのである。
・日本国内の勤労所得は減少するが、海外企業への投資収益、知的財産への支払い、など
は大幅に増える。海外で働く人材の所得も大幅に増える。これらを合わせれば、国内で
減った所得を大幅に上回る所得が得られる。国内所得であるGDPではなく、この合計
所得を増やすことが政策目標になる。このためには、何よりも円高が必要である。海外
の企業を買収し、人材を買収し、雇い入れるには、通貨の力が必要である。
・日本の資産のほとんどは円建てである。我々の購買力は、消費者も企業も金融機関も円
である。1980年代末のバブル期、米国の象徴であるロックフェラーセンター、映画
残業を買収し、米国を日本が乗っ取るというイメージだけ喧伝されたのも、円高という
迫力があったからだ。急速な円高にもかかわらず、円高不況という言葉も乗り越えて、
日本経済は世界を席巻した。通貨の強さとは国力なのであり、米国はこれを恐れたので
ある。現在は、日本の相対的存在感は圧倒的に低下している。日が沈む国とたとえられ
ている。そこで、円高になっても恐怖感はない。だから、円安を円高に戻しても、アジ
アの一部の国に歓迎されこそすれ、国際的にはまったく問題にならない。
・円安を非難しない最大の理由は、欧米はもはや通過安競争の枠組みにはないということ
だ。欧米は強い通過を欲している。自国経済を強くするためには、自国の利益のために
は、通貨が強いほうが圧倒的に望ましい。もはや資産のほうが重要であり、政治的に労
働組合などがうるさいが、全体では圧倒的に強い通過を望んでいるから、日本が勝手に
通貨を弱くしてくれるのはだい歓迎なのだ。
・これまでの政策の間違いは、できもしないことをできると言ったり考えたりしてきたこ
とによる。産業の有機的な発展は、国家主導ではできないし、それは健全は発展を阻害
する。国家は補助的な役割に自己を限定し、しかし、それを徹底的に果たす。補助的は
役割とは、まず、円高により、日本という地域の経済力を強めることである。日本地域
の経済力が高まれば、そこを拠点とする企業と個人の経済力も高まる。立場も強まる。
・企業と個人は、個々が強くなければならない。地域の力を強めるのは個である。企業と
個人がすべての基本である。だから、人を強くする。企業は人なりである。国家も人な
り、だから、人を、個人を徹底的に育てる。政府がそれを支える。
・デフレとは不況ではない。デフレとはインフレの逆であり、物価が上がらないというこ
とであり、それ以上でも以下でもない。景気が良く物価が上がらなければ、それは最高
だ。あえて無理にインフレにする必要はまったくない。
・所得が下がったのはデフレが原因ではない。デフレは結果である。所得が下がり、需要
が出ないからモノが高いままでは売れないので、企業は価格を下げた。効率を上げて、
価格を低下させても利益は出た企業は生き残った。バブルにまもれて、高いコスト構造
を変革できなかった企業は衰退した。そもそも日本の物価は高すぎた。
・デフレ社会が望ましいのは、同じコストでより豊かな暮らしができるということに尽き
る。所得が多少減っても、住宅コストが低ければ、経済的にもより豊かな生活が送れる
ことになる。
・最近の若者は、職場の同僚や上司と飲みに行かないと中高年サラリーマンは愚痴ったり、
団体行動ができないと批判したりするが、それこそ無駄の排除であり、極めて望ましい。
給料の一部を無駄遣いして、時間を浪費し、家族との時間を減らすことは究極の無駄で、
その無駄がなくなるということは、日本社会が効率化していることの現れだ。飲み会は、
友達の家で家飲みをすれば、低コストで、よりくつろげ、友情もより深まり、何より楽
しい。会話も、家の家具、かける音楽、料理のレシピの話、キッチンツールの話と、よ
り実のある、そして、人間の本質の現れる話になる。バーカウンターではったりをかま
して女性を口説くことなど、単なる無駄を超えてインチキであるから誰も望まない。草
食は生態系でも効率的だ。これこそ効率的な社会である。
・東京の一極集中は効率が悪いので、地域ごとの自然な発展を促す。それによって、これ
まで日本がつくり上げてきた各地域の豊かな社会資本、環境、地域社会を有効活用し、
社会のち蓄積、ストックを経済的にも活用し、社会として豊かさを享受する。
異次元の長さの「おわりに」
・成長の時代は終わった。もはや経済成長を求める時代ではないのである。それは成熟経
済だ。成熟とは何か。経済を最優先としない経済社会である。経済は所詮、手段でしか
ない。所得も、何かを手に入れるだけの手段に過ぎない。だから、手段は手段として割
り切り、状況、環境に合わせたものを選択するのが当然だ。その当然のことを自然にで
きる社会。それが成熟社会であり、成熟社会経済だ。
・日本経済は、世界経済とともに動いている。経済は生きている。変化する。生きている
経済は、政策ではコントロールできない。にもかかわらず政策で経済をなんとでもでき
ると思っているエコノミスト。政策にすべての経済問題を解決することを迫る有識者、
メディア、世論、雰囲気。それに応えようとする政治。それで選挙に勝とうとする政党。
コントロールの誤謬。政策依存症候群。この二つが解消されなければ、日本経済の未来
はない。日本経済は成熟できない。日本社会は未熟のまま、衰退していく。これが日本
の終わりだ。
・成熟社会とは、現実に柔軟に対応できる社会である。どのような変化、ショックが起き
ても、円熟したベテランとして、それを受け止め、その中でベストを尽くし、さらには、
その新しい環境、逆境をもむしろ活かすことにより、さらに円熟することができる社会、
経済。これが成熟社会経済だ。
・経済はどうなるか誰にも予想できないのであり、予想できたとしても何かが起これば変
わり得るのだから、経済の変化で制度が破綻するような制度をつくってはいけないのだ。
将来の経済状況の予想により左右されるような制度は、根本的に誤りだ。
・若者が減ると活力が失われる。しかし、活力を失った若者が大勢いる。都会は若者不足
ではない。むしろ多すぎる。いろんな傷を負った若者が多すぎる。若者を増やす前に、
ブラック企業によって壊される若者を守らないといけない。
・若者が結婚するように結婚する金銭的インセンティブを与える。子供を持つように金を
配る。そんな対症療法は意味がない。前提条件を整えることが政治の役割だ。政策だ。
人間的な生活を送れる環境をつくり、労働環境を整え、ワークライフバランスなどとあ
えて言わなくてもいい雇用となるようにする。そうすれば、若者は人間的な生活を取り
戻す可能性がある。それでも結婚も出産も増えなければ、それが今の社会だということ
だ。
・子供を産ませるのではなく、託児所が機能するようにすればよい。そうなれば、子供を
持つかどうかは、各人の選択だ。子供を増やすために婚外子を法的に認める?婚外子を
社会的に精神的に受け入れる土壌がなければ、意味がない。
・現象に対応するのではなく、根源にアプローチするのだ。そうでなければ、現象が収ま
っても、また別の問題が起きる。より大きな問題となって、ひずみとなり、ひずみはシ
ステム破綻の危機となる。まさに今の金融緩和と同じだ。
・GDPの増加率が、人口が減ると低下する。マイナスになる。労働力が減ると生産力が
落ち、GDPが減少する。だから、人口を増やさないといけない。これは最悪の間違い
だ。我々は社会の中で生きている。経済は手段だ。手段と目的を取り違えてはいけない。
所得増大は手段だ。目的はいい社会をつくること、維持すること。経済規模は手段に過
ぎない。一人当たり国民所得ですら手段に過ぎない。社会が荒んでいれば、所得が2%
ぐらい増えたって、まったくいい社会ではない。豊かな社会ではない。
・社会の在り方として、若者が少ない社会は良くない。問題はそこだ。この価値観を支持
するなら、まず、若者をきちんと育てよう。社会で育てよう。甘やかして弱い若者をつ
くってはいけない。少子化の一番の問題は、過保護になることだ。両親が子供を祖父母
に預けることの最大のリスクは、かわいがりすぎることだ。一方で、愛を受けずに育つ
リスクはもっと深刻だ。
・国のために増やすのではなく、子供を育てたい両親がそれを実現できない障害があれば
取り除く。政策にできることは、それだけであり、それで十分だ。
・アベノミクスとは、問題の裏返しそのものだ。異次元の金融緩和とは、現象への対症療
法に過ぎない。一時しのぎに過ぎず、よりおおきなシステムリスクを呼び込む政策だ。
昔の日本経済に戻ることはできない。円安で輸出して不景気をしのぐ時代は終わった。
価格競争で通貨を安くして輸出を増やす時代は終わったのだ。
・金融政策はあくまで補助だ。インフレを起こして一挙解決、デフレ脱却ですべてが解決。
それは間違いだ。安直だ。堕落だ。社会システムのデザインの放棄だ。金融政策は、あ
くまで補助だ。実体経済が、企業が、個人が、投資、生産、消費へと動くのを、じっく
り待つ。それらが足りないときは、動くたくなったら動くように、場を整備しておく。
金利を低く抑えておく。
・一方、金融引き締めのときには、中央銀行の側から動く。能動的にブレーキをかける。
しかし、これも、動きが感じられないくらいの動きが理想だ。ブレーキを感じない、必
要性も感じないように、経済が順調に安定していることが理想だ。バブルに対して急激
に引き締めるのではなく、バブルを膨らませないのが中央銀行の仕事だ。
・景気対策はしない。財政対策による景気対策はしない。金融政策による微調整にとどめ
る。金融政策でGDP増加率の底上げはしない。ショックは和らげる。変動は少し緩和
する。しかし、それ以上はやらない。すべては、長期的な健全性にささげる。金融市場
の安定性を守る。
・政府の政策は、社会政策に絞る。経済成長ではない。人を育てる。健全な人間を社会が
育てる。その環境を整備する。労働力として、経済成長の歯車としての労働力を育てる
のではない。健全な人間が育つようにする。健全に育てば、生きるためにきちんと働く。
生きる意欲、生きる活力を持った人間が育つ。そういう人間は自然と意欲を持って働く。
そのときに、政府が補助する。これこそが、長期的に持続可能な社会を生み出す唯一の
道であり、その結果として、経済は自然と健全な発展を遂げ、成熟するだろう。
・成熟社会においては、トップダウンアプローチは通用しない。政府が有望な産業を指定
し、資源を投入する方法はうまくいかない。なぜなら、個は多様であり、トップダウン
で一つの方向に結集することはできない。するべきでない。個が多様な力を発揮できる
ような場の整備、場のデザインが政府の役割だ。
・つくり込み過ぎてはいけない。街づくり、住宅設計、オフィス設計と同じだ。街も家も
職場も、そこで生きる人間がつくるものだ。フレームはつくるが柔軟で、そこで生きる
人間が調整できるものであり、フレームが合わなくなったら、個々の生きる人間が修整
する仕組みだ。無理矢理つくった街、計画都市はほとんど成功しない。よく練られた柔
軟な計画だけが成功する。
・政治家も評論家も、安易にすべてを投げ捨て、ゼロクリア、ゼロスタートを叫ぶが、そ
ういう人々は、壊すことだけしか考えないし、行わない。好き勝手に新しく自由に制度
をつくれると思っていたら、彼らをデザイナーにしてはいけない。
・現代において、すぐに制度をゼロクリアするような提言をする人間は信用できない。間
違っている。必要ない。社会を破壊するだけだ。代案なしに、代わりのデザインなしに、
社会システムを破壊すれば、混乱、無秩序が訪れるだけだ。
・岩盤規制、既得権益をぶっ壊して競争させても、競争自体は何も生み出さない。自由に
行動できるようにすることが重要なのであって、競争自体は殺し合いもあり、ライバル
を倒すだけの戦いになる。競争自体ぁらじゃイノベーションは生まれない。自由な選択
肢からしかイノベーションは生まれない。しかも、本質的には、創造性は制約条件の下
でしか発揮できない。自由過ぎては、何も生まれない。今必要なのは、革命ではなく、
ヴィジョンの修正に過ぎない。それで十分だ。しかし、それは十分に行われていない。
・人々も企業も、ちゃんと地に足をつけて生きている主体は、すでにわかっている。日本
は成熟社会になったのだと。だから、円安になったからと言ってむやみに安売りをして
輸出を増やそうとしない。製品の価値を維持し、ブランドを維持し、次の製品に備え、
次の市場に備えるのだ。
・所得水準は、これから平均ではそれほど伸びない。世界の競争は激しく、日本だけが勝
ち残ることを無邪気に期待するわけにはいかない。生産の多くは途上国、新興国にゆだ
ねることになる。国内の働き手は、国内サービス産業を中心に雇用を得ることになる。