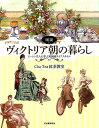経済的に強い国とは言えなくなっているが、かつては産業革命の発祥の国であり、世界を制覇した国
である。国力の盛りを過ぎ、人間で言えば中年期となったイギリスではあるが、そこには成熟した人
びとの生活ぶりがある。
右肩上がりの経済成長を続けてきた日本も、今や峠を越え下り坂を降り始めている。もはやこれ以
上の成長を望めない日本の人びとは、これから何を目指せばいいのか。私は、イギリスを大いに参考
にすべきであると思っている。経済的には豊かになった日本。しかし、本当の意味での豊かさをあま
り感じられない。本当の豊かさとはどういうものであるのか。そのヒントがイギリスにあるような気
がする。イギリスの人びとのような、質素でつつましいが豊かな生活。これこそこれから日本の人び
とが目指す生き方ではないだろうか。本書はそんなイギリス人の生活ぶりを知るには、大いに参考に
なると思える。
・イギリスの日常生活は、自然とのすこぶる深いかかわりによって支えられている。イギリスとい
う国は、ロンドンのような大都会でも、ちょっと郊外へ行くと、人びとの家にはかならず、玄関
先に小さな庭があり、裏側にまわれば、それよりも何倍も広い芝生の庭がある。
・隠居した者は、庭先の木立の間に、ハンモックを吊るして、天気のよい日にはそこで読書を楽し
む。生活は経済的には決して楽ではなさそうだが、悠々としてゆとりのある暮らしを享受してい
る。
・イギリスは、北海道よりも北に位置するのだから、夏でも気温が25度を超えることは少ない。
まるで避暑地のような気温で、空気はからっとして、ロンドンのような大都会でも空は青々とし
ている。
・イギリスは、「緑の国」と呼ばれる。ほとんどの土地が緑の牧草とか、芝生で覆われているから
なのである。冬でさえそうなのだから、夏には異常気象さえなければ、公園も広場も、川や山や
丘や野原や牧場も、すべての大地が青々としている。
・伝統的に園芸の愛好者が多いイギリス人は、夏の期間にはわが家の庭に美しい花を絶やすまいと、
庭仕事に精を出す。芝生刈り、生垣の剪定、庭の水やり、堆肥づくりなどなど、仕事はつきない。
こういう仕事にかかる時の紳士の服装は、プロの庭師と同じである。
・夏の水辺でイギリスらしい過ごし方としてあげられるのは、家族によるボート旅行であろう。
18世紀に水上運輸の役割を果たした運河は、イギリスの各地にめぐらされていて、水門を利用
するなら、ほとんど全国各地へのボート旅行ができる。イギリスならではのレジャーである。こ
の一見豪華に見えるレジャーは、日本人の平均的なレジャー費の何分の一かで済むところが羨ま
しい。イギリス人の生活は決して派手ではない。ボートでの食事にしても、お昼はサンドウィッ
チ、夜は肉料理と野菜といった簡単なものである。それでも、ボート旅行は、豊かな気分に満ち
溢れている。
・イギリス人は、隣の家の庭に負けまいと、その庭の花づくりに一生懸命に丹精をこめるが、そこ
に住む人びとの生きがいのようにもみえるが、彼らはただ隣の家と競争したり、見栄を張り合っ
ているのではない。イギリス人の家の庭は、日本人の家のように庭の垣根は高くないので、まる
で両側の家々の庭は、公園の花壇を思わせる。歩行者が花の美しさをめでられるように、庭の垣
根をわざわざ低くしているのである。
・イギリスで居間とか書斎に備えられている椅子は、読書に適している。あまりに快適すぎて、い
つの間にか居眠りをしてしまう。読書は楽しむものだからそれでもいいのだ。日本人のように、
物事を堅苦しく考えない人たちだから、眠たければ眠ればよいというのがイギリス流である。
・イギリスの家庭は、たいてい家の隅々まで厚ぼったいじゅうたんが敷き詰められている。イギリ
ス流でちょっと理解に苦しむのは、読書用に灯りの暗さである。イギリス人はむかしから、暗い
灯火の下で読書をしてきたにちがいない。
・イギリス人の早朝の楽しみは、アーリー・モーニング・ティである。それは、ミルク・ティに決
まっている。
・基本的にはイギリス人の生活感覚は、楽天的のようである。彼らの多くは決して悲観論者ではな
く、あまり細かいことにこだわらず、大らかで寛容である。生活の喜びを知っている人が悲観的
になるわけがない。豊かな自然が生活の身辺にあると心が豊かになるから、それほど生活が贅
沢になることがない。そんなにあくせくすることも、悲観することもなく、自然のままに生きる
ことに大切さがわかってくる。
・イギリスでピクニックという習慣が一般的に定着しはじめたのは、19世紀後半以降のことであ
る。この時代、イギリスは今日の日本同様に、未曾有の経済的繁栄をなしとげ、中流階級の人び
とがその発展によってもたらされた余暇を、日常生活の中でようやく享受できるようになってき
たからである。
・1880年代からは、イギリスで自転車が大流行となり、大きなバスケットに食料や飲み物を詰
め込み、せいぜい1時間くらいで行ける行楽地へと遊びに行った。経済的安定にともない、よう
やく自由になった休日を、家族や友人たちと過ごすことができるようになったのである。
・イギリス人のピクニック習慣に、商業主義はなじまない。ピクニックの客を相手に商売をしてい
るのは、せいぜい個人的にやっているアイスクリーム売りぐらいであって、大もうけをたくらむ
商業主義は、イギリスでは見当たらない。ピクニックは本来、家族の時間を楽しむためのもので
あって、行楽地での浪費を楽しむなどという習慣ではないからである。ピクニックにでかける人
びとは、行き先で余計な浪費をしなくてすむように、必要な食べ物や飲み物など、ほとんどホー
ム・メイドのものを用意する。イギリス人のピクニックは、ただ単に自然を求めて出かける場合
だけとはかぎらない。競馬でも、ボート・レースでも、野外コンサートも、それらの見物はピク
ニックに化ける。
暖炉と庭と田舎暮らし
・東京の中心街の華麗さに比べれば、ロンドンの街頭は古ぼけて見える。また路上の人びとの服装
や身なりを見ても、よほど日本人の方が高級服を身に着け、よい物を持ち歩いている。しかし、
もっとよく眺めて見ると、社会構造と人間のライフ・スタイルは、まったく別物であることに気
づくのである。
・社会のインフラ構造といわれる基礎的な諸設備では、イギリスほど完成された国は少ないであろ
う。ひとつ具体的な例では、イギリスの全土、電柱の地中への埋設は、ほぼ完全に近く行われて
いる。
・日本も光ファイバー設備に巨額な投資をする前に、すくなくとも、日本中のバス路線だけでも電
柱の地下埋設を優先すべきである。まだ基礎的な社会インフラが未完成というよりも、すこぶる
脆弱なのに、ブローバンド化を急ぐのは本末転倒ではないのか。日本の個人的な日常生活の内実
が、経済の進歩に見合わず、すこぶるちぐはぐであることは、もはやこれ以上述べるまでもない。
また、意味のない消費は、家庭生活における真のゆとりの実現とはなんの関係もない。
・英国の社会は、日本よりもはるかに多様性に富み、ダイナミックな感じがする。ロンドンの駅に
朝乗り降りする英国人の服装は、東京駅の朝の通勤族ほど整っていない。
・英国の女性たちは、今日ではその大半が職についている。40年ほど前、アメリカから英国に渡
った時まず目につくのは、女性たちの足の太さであった。しかし、今日、ロンドンの街角を歩い
ている女性たちは、いずれもすらりとした脚線美の持ち主である。その変化は、彼女たちのライ
フ・スタイルの変化と大いに関係があると思われる。
・イギリスの住宅街が、日本のそれと異なって整然と見えるのは、ひとつの街区にある住宅は、す
べてその様式が統一されているからである。しかし、その外側の印象とは正反対に、その内部は
すこぶる華麗で、それぞれの家のインテリアは、どの家も決して画一的ではなく、きわめて個性
的である。
・イギリス人の家に欠かすことができないものは、暖炉である。彼らが家という時には、そこには
必ず暖炉がある。
・こうしたイギリス的なライフ・スタイルは、実をいうと我々日本人も、ついひと昔前までは身に
着けていたのではないだろうか。
・イギリスの住まいや、イギリス人の生活感覚は、意外にわれわれ日本人と共通した部分がある。
自然の調和を求め、家のどこかにいつも花を絶やさない彼らの生活感覚は、人間として生きる喜
びをしっかり見につけている。
・イギリス人の生活規律は個人主義であるけれども、町並みに関しては、その地域の全体性が重視
されているようにみえる。日本人は常に全体性を重んじ、あまり個人主義的規律にはなじまない。
それなのに日本の町並みを見ると、各家々はてんでばらばらで、そこには美しい調和がほとんど
見られない。
・イギリス人の家は、外観から見る限り、どの家も同じようであるが、その家の玄関に入ると、外
側とは対照的に、家の中の感じが個人的なのに驚かされる。
・今日イギリスではよほど辺鄙な田舎へでも行かない限り、電柱のある風景はない。パリは電柱の
点でも、ロンドンには及ばないし、ちょっと郊外に行くと、電柱のある風景が目につく。アメリ
カの西部のロサンゼルスやサンフランシスコのような大都市でも、中心街を離れると電柱は目立
ってくる。
・イギリスでは新聞の宅配はごくまれであって、読者はたいてい新聞店とか、街頭の新聞スタンド
などで買い求めなくてはならない。新聞店はふつうのコンビニエンス・ストアとか、書籍文具店
の兼業で至るところにある。新聞は朝刊と夕刊と日曜版とがあり、日曜版は日本のお正月の新聞
くらい分厚いもので、これを日曜日の朝買いに行くのは、男の仕事と決まっている。
イギリスでは高級紙と大衆紙の読者は歴然と分かれている。高級紙の発行部数はいずれも50万
部から80万部であり、大衆紙のそれは200万部から500万部ぐらいで、日本の大新聞とは
比較にならないほど少ない。
・ロンドンは歴史の煮つまったような町である。市の中心部の外観は、外周部ほど美しく整然とは
していない。
・整然と造られた都市は、合理的で住みよいかというと、必ずしもそうとばかりはいえないと思う。
人間の存在そのものが本来非合理的なものだから、町の中に歴史的な非合理性が存在することに
よって、そこに住む市民はどれだけ情緒的な安定を得られるかわからない。
・イギリスのお年寄りたちの行動パターンは、概して個人的傾向が強い。せいぜい夫婦単位である。
日本でよく見かけるようなお年寄りグループとか、地域のお年寄りがみんなでゲート・ボールに
興ずるといった光景は見当たらない。
・イギリスでは退職すると1時間ばかりで行ける郊外に、古い木造の家を買い取り、その家の内部
を住みやすいように手入れをしてカントリーライフを楽しんだりしている。
・イギリス式庭園は自然のたたずまいを生かしたものが多く、屋敷の中を流れる小川に、木橋を架
け、樹木を植え、小径をつくり、花を植え込み、素晴らしい自慢の庭ができあがっている。
・イギリス人のほとんどは、自分なりのライフ・スタイルを持ち、自分自身の価値基準で生活を楽
しんでいる。自分の周囲を見渡して、自分の行動を決めるのではない。そこにはイギリス人の根
強い個人主義的な精神があるが、それは決して反社会的なものではない。
・お年寄りが地域の中で、どれだけ充実した生活を送れるかは、単に福祉行政の問題だけではない。
市民ひとり一人の意識とか、社会そのものが美しく成熟していなければ、お年寄りの生活は決し
て豊かなものにはならないことが、イギリスの社会を見るとよくわかる。
・日本のパン屋さんの店先にならんでいる、おなじみのイギリス・パンというあの山高パンは、今
日では本場イギリスではほとんど見かけることがない。イギリスの朝食用にもちいられるトース
ト・パンは、極端な話が山低パンである。その高さは10センチあまりで、横幅の方が広い。こ
れは今日の電気トースターにも便利につくられている。
・イギリスのトースト・パンは、こんがりと焼いてパリッとした感じを楽しむのである。フランス
人の朝食はバゲットが主流で、時々クロワッサンのような高級パンを食べるのが普通だが、ドイ
ツの上流志向の家庭ではイギリス風のトースト・パンで朝食を取るのが、社会的ステータスの象
徴とみなされているらしい。オランダもこの傾向がある。
・イギリスではまだ靴の修理屋は健在である。これはイギリスでは日本やアメリカのような使い捨
ての大量消費の生活が広く社会的に支持されていない証拠である。
・イギリスの街路は、どこに行っても舗装が完備しているので、決して靴が汚れることはない。だ
から家に入るにも、外を歩いてきた靴を玄関で脱ぐという習慣はない。その代わり、玄関にはマ
ットが必ず置いてあって、中に入る前にそのマットで何度も靴を拭うことになる。
・今日のイギリスの犬たちのマナーのよさは、決して昨日や今日出来上がったのではなく、少なく
とも、近代200百年の歴史の中で完成したものなのである。イギリスでは犬もまた人間と同じ
ように犬権というべきものが確立されているようにみえる。ロンドンのタクシーには犬と相乗り
についてはいくらとはっきり書いてある。イギリスの犬の生活は、確かに恵まれているように見
える。その理由は言うまでもないが、イギリスの社会からきちっと人間的にできあがっているか
らである。
・ユーロトンネルプロジェクトに対して、イギリスは国家予算をほとんど支出していない。せっか
くの新幹線もイギリス国内では時速130キロにスピードダウンしなければならないという。イ
ギリスの国民の大多数は、海峡トンネルの開通にほとんど関心を持っていないのである。国民の
6割が海峡トンネルの新幹線利用に否定的な態度を示していた。
・イギリス人の多くは、真っ暗な海底を超スピードで走りよりも、これまでのように連絡船に乗っ
て、ゆっくりと船旅を楽しみ、そしてあの美しい白いドーヴァーの絶壁を眺めることに郷愁を持
ち続けるにちがいない。我々日本人ならば、古い連絡船など見向きもせずに、どこかの会社に売
り渡したり、スクラップにしてしまう。
・イギリス人は新しいものへの対応が遅い。現代の経済競争で、アメリカや日本やドイツに敗れた
のも、新しい生産システムや経済方式への対応に「リラクタント」であったことが大きな原因で
ある。ロンドンの街では、ほとんど自動扉を設けている店舗はないし、タクシーの車体はもう何
十年もモデルチェンジを行っていない。
一杯のおいしい紅茶
・イギリスでは紅茶が美味しいことは言うまでもないが、気象の条件なども、紅茶飲みに適してい
るのではないかと思う。つまり空気が乾燥していて、いくらでも紅茶が飲めるのである。たいて
い、一日に6,7回は飲んでいる。
・イギリス人が普通淹れる紅茶はミルク・ティと決まっている。普通英国紅茶はミルク・ティと考
えてよい。そして紅茶とともに出されるミルクの量が、これまたすこぶる多いのである。ミルク
は温めないで冷たいものを使う。ミルクを温めると、その匂いが紅茶を駄目にしてしまうからで
ある。
・イギリス独特のティ・タイムは、生活の中でのゆとりの表れ、つまり精神的なゆとりを反映した
ものと言える。イギリスが世界に誇れるのはシェイックスピアであり数々の詩人たちの言葉の芸
術なのである。加えて産業革命発祥の地であったイギリスでは、世界に先駆けて消費生活を堪能
し、19世紀初めにはそんな生活からさっさと卒業してしまった。彼らは実用性があり、美しく
耐久性のあるものがいいものだという価値観のもと、つつましいながらも質を充実する術を発展
させていった。それがティ・タイムに凝縮されているのである。
・おそらくお茶をもっとも愛好し、それを文化様式ないしは芸術にまで高めた民族は、日本人とイ
ギリス人ではないだろうか。しかし、茶道はたしかに生活芸術であるが、非日常的要素が濃厚で
あり、その高雅な精神性は、日常生活にゆとりを見出せない庶民にとっては、長い間まったく無
縁のものであった。