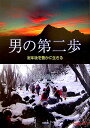して、山口百恵の「蒼い時」をプロデュースしたことで、広く知られるようになった人で
ある。元アナウンサーの女性で、本を出している人はけっこう多いと感じる。すでに70
歳近い年齢になっているのであるが、それでも、もう一度花を咲かせようとはどういうこ
となのか。興味を覚えて読んでみた。
しかし、このような本に登場してくる人たちは、大抵は、元会社の社長だったり役員だっ
たり大学教授だったりで、最近のはやり言葉で言えば、「上級国民」に分類される人たち
だ。筆者たちは、いかにも自分たちは一般国民を代表する普通の人たちなのよ、と思って
いるらしいが、どう考えても我々が考える普通の人たちではない。そのあたりを割引いて
読まないと、自分の現実との違いを見せつけられるだけで、ただただなんともやるせない
気持ちにさせられるだけのような気がする。
本の内容はというと、これは女性が自分のこれまでの日常生活での出来事を、思い出しな
がらおしゃべりしたのを文字にしたような内容だ。こういうおしゃべり的なものは、女性
の書いた本に多く見られる気がする。女性が得意とするところなのだろう。男性の書いた
本にはあまり見られない。筆者は雑誌の世界に身を置いてきただけに、本の内容もまさに
「雑」情報で溢れており、筆者が雑誌の世界で生きてきたということが、色濃くでている
感じがする。筆者は、この「雑」のなかにこそ正統や権威と無縁の真理が潜んでいるとの
信念を持っているようだ。そしてこの「雑の世界」をすくい取る力が必要なのだとのこと
のようだ。しかし、この「雑の世界」から真理をすくいとるのは、なかなか難しい。
この本の文中に、その理由らしきものを発見した。筆者はブシャール結節とへバーデン結
節という指の関節が腫れる持病があることが書かれていた。実はこの病気は、私の連れ合
いも悩まされている病気なので、その辛さは他の人よりは理解しているつもりである。筆
者はペンを持つことも困難になったという。この本は、筆者が語った内容を他の人が文字
に起こしたものかもしれないと、自分勝手に想像したりしている。
・本当に自分のやりたいことを成し遂げるためには、いくつもの扉を開けたまま「あれも
これも」と手を出すのではなく、いったん自らの手で扉を閉じて的をしぼろうと思った。
そうでもしないと、残存時間と残存エネルギーを考えた時、結局は中途半端になり、や
がて他者から扉を閉められてしまうと思ったからだ。
・会社をリタイアしても、人生は終わってはいない。還暦になろうが古希になろうが、そ
れがどうしたというのだ。喜寿だって100歳までにはまだ23年間もあるのだ。
・昔は私たち団塊の世代は人口が多いというだけで、ただ待ってさえいれば物も事も向こ
うから舞い込んできたが、今は保有財産を狙ってアプローチをかけてくる輩ぐらいしか
近寄ってはこない。
・やりたいことがある。やり残したことがある。このまま終わりたくない。これからは自
分のためではなく、社会のために生きていきたい・・・。そんな気持ちが少しでもある
のなら、思い切って新しい一歩を踏み出そうではないか。
・親しき友が志半ばで逝き、何人かは病と闘っている。50歳過ぎれば身体にいくつかの
故障箇所があるのは当たり前だ。かろうじてでも元気なら、今からでも遅くはない。自
分の手で、自分が生きている証を創ろう。
同世代はこんなことをしている
・最近、リタイア後に時間を持て余している男たちが多くなってきた。家にいれば妻の日
常に支障をきたすくらいのことは分かっているので、夫たちはなるべく外に出ていく。
・朝食後、新聞を持ってコーヒーショップに行き、紙面を広げては社会とつながっている
ことをアピールしているシニア男性が少なくないと聞いた。実際に見に行ったら横1列
5人の男たちが一言も交わさずそれぞれ黙々と経済新聞を読んでいた。まだ心身ともに
元気なのにここ以外「居場所」と「役割」がないみたいだ。
・過日のアメリカ視察で印象に残ったのが「男の隠れ家」だ。庭の片隅に手作りの小屋を
建てたり、裏を改造して、なるべくお金をかけずに自分の工夫でコツコツ作り上げてい
る感じだ。
・私の友人のご主人も「男の隠れ家」を持っていて、裏庭の坂を下りた所に造った隠れ家
は趣味のいい丸太小屋という感じだ。
・コーヒーショップで新聞を読むのもいいが、少年時代、蔵の天井裏や押入れの中で「隠
れ家ごっこ」をしていた頃を思い出して、子どもが出ていったあとの部屋や居間の隅に
自分だけの「遊び場」を作ってはどうだろう。
・友人たちをみると、現役時代は必死にITを取り入れて頑張っていたのに、定年後は
「やっぱりデジタルよりアナログ、バーチャルよりリアルのほうが人間的だよ」と、ス
マートフォンを電話としか使っていない人が増えてきた。
・かくいう私も「IT弱者」ではあるが、新しいものへの好奇心だけは失いたくないと思
い、最近、最新式のスマホを購入した。
・新しいものにトライすることは、新しい物を受けつけない頑な先行保守世代よりはずっ
とマシだと思う。
・私も新しい物が登場したら「食わず嫌い」はしないことにしている。一応はかじってみ
て自分に合わなかったらそこでやめればいいのだし、まだ何かありそうだと思えばしば
し付き合ってみることにしている。
・少し前まで同世代の女性の間で、娘が離婚して孫と一緒に実家に戻ってくる「孫連れ出
戻り娘」を歓迎する向きがあった。ところが最近は、男親が実家に戻った娘を歓迎して
いる事例が増えている。男友だちは定年を迎えた今も週3日は関連会社で働いているの
だが、「娘が孫と一緒に家にいるので毎日が楽しくで。仕事に行きたくなくてねぇ・・
・」と、相好を崩していた。「妻はあまり嬉しそうではないんだけど、僕は夫婦だけの
殺伐とした毎日に比べたら笑い声が絶えない今の生活は楽園にいるみたいだ」と彼は言
う。孫との生活を送る中、男友達は新しい「仕事」を見いだしたらしい。
・いざとなれば親に返却できる孫育てと、何があっても逃げられない子育ては根本的に違
うのだが、人生の終盤近くにせよ、男たちが育児体験をすることは、悪いことではない
と思う。
・「人生100年時代」という言葉を初めて聞いた時、労働力人口が足りなくなったので
シニアをもっと長く働かせるための「たくらみ」だろうと思ったのだが、どうやらこの
言葉、女性より平均年齢の短い男性にウケがいいらしい。
・最近、男友達が「人生100年」を意識した新しいライフプランを疲労してくれた。彼
は、長野に別荘を建て木曜日の夜から月曜日の朝までは農業にいそしんでいて、いずれ
は田舎暮らしをするだろうと想像していた。ところが、「人生100年時代に、こんな
ことをしてはいられないと思ったんだ。100歳は無理でも80歳までは十分働けるよ
ね。今は63歳だから、あと17年もあるんだよ。再度東京を拠点にして、仕事をもう
ひと頑張りして世のため人のために何かやろうと思ってさ」と言ったのである。
・今春古希を迎えて社長から会長になったばかりの男性は「好きなことをするのもいいけ
れど、70歳を超えてもこんなに元気なんだから、もっと社会のためになることをしよ
うよ。少し退いて世の中を見てみると、このままではこの国はもたないと思うんだ。こ
うなったのは僕たちにも責任があるでしょ。僕たちが世直しをしないで他に誰がするの
よ」と提案した。とにかくこの世代の男たちは、課題を抽出して議論をするのが好きな
人が多いので、もしかしたらこの会も議論だけで終わってしまうかもしれない。それで
も、自分の「好きなこと」だけに時間を費やすよりはずっとステキだ。
・「地方消滅」の危機が叫ばれ、地方再生が急務となっている昨今、地方自治体も「空き
家バンク」などを作り、移住推進に力を注いでいる。数年前まで移住にメインターゲッ
トだった60代は脇役に回り、最近では30代、40代の移住が主流だ。
・若い彼らは生き方そのものを見直したいと考え、農業や漁業に新規参入をはかったり、
カフェや民宿を開くなど地域経済にも貢献している。
・そんな中、近ごろ私の周りでは京都移住に踏み切った「アラ古希」世代が目立っている。
夫だけが望む一方的な「田舎暮らし」に妻が同調できず、「卒婚」や離婚になることも
珍しくないと聞くが、優雅で知的な匂いのする京都暮らしに反対する妻はいないという
のも京都移住が増えている一因らしい。
・実は、私も最近はとみに年齢を感じていて、今の自分の年齢を口に出すのはためらいが
ある。還暦から64歳までは平気だったのに、65歳以降はできるだけ年齢をいいたく
ない。いっそ70歳を過ぎれば言いやすいような気もするが、60代後半というのは中
途半端で、老いと若さをどう分配したらいいのか分からないのである。若作りをし過ぎ
るのも変だし、自然体がいいからと思っても、シミやシワやクマを放置しておくのも気
が滅入る。
・一つ年上の男友達は、友人のデザイナーにつくってもらったというモダンな作務衣を着
て会いに来た。「どんなに頑張っても年はとるから、ここらで表面的な若さを求めるの
はやめて、生き方がカッコよく見えるジジイになろうと思ってさ。これからの農業をや
ろうと考えているんだ」最近ではほとんど絶滅してしまったと思っていたが、外見か中
身はともかく、いまだに「自分は人にどう映るか」を気にし続けている団塊男がいるの
は、大きな励みだ。
心機一転!残間の日々
・数年まえまでは積極的にデパートやブティックを回ったが、母の遺品整理をしてからと
いうもの、あまり気が進まない。母の遺品が膨大な量で整理が大変だったから、息子に
同じ苦労をさせたくないとの気持ちもあるが、私の寿命を考えると「今、買ってもそん
なに活用しないのではないか」とつい及び腰になってしまうのだ。
・後先を考えずに買い物をしたのはバブルの時だった。「なぜこんな物を」と後悔してい
る大きなイタリア製のソファや毛皮のコートなど、私に不釣り合いな物はみなバブル期
に買った。
・今、当時購入したモノたちを見ると「恥の歴史」の産物という気もするが、あの頃は元
気だったのでまだまだ自分の可能性を信じていたのだと思う。
・リーマン・ショックの頃も買い控えたが「人は新しい物を手にしないと気持ちが後ろ向
きになって活動が止まってしまうよ」とたしなめられて買い物劇を再開した。
・それでも購入しているのは主に洋服で、心の奥底い「断捨離」とか「老いじたく」とい
う言葉があって、家具や食器、美術品などは後々始末が大変だろうと避けている。旅行
のお土産も食べれば消える食品ばかりで、間違っても民芸品の人形や置物は買わない。
・たしかに、新しいものを取り入れない生活を続けているうちに、日々、消極的で地味に
なっていく自分を感じる。行動力も活力も衰え気味だ。
・東京ドームで開催されていた「東京国際キルトフェスティバル」で、山口百恵さんの作
品が展示されていると聞き、身に行った。会場は妻が自作を見せるために連れてきたと
おぼしき夫たちを見かけるぐらいで、男性客はほとんどおらず、大人の女性たちであふ
れていた。百恵さんの作品は、やはり注目の的で、ここだけは通行が規制されていた。
作品は29年間続けてきただけことはあって趣味の域をはるかに超えていた。
・手指にブシャール結節とへバーデン結節を持病に持つ私に手芸は工芸は無理だが、キル
ト展を見ながら「趣味を持たない私」を改めて認識し、仕事がなくなったあとでやるこ
とを早く探さなければと思いながら帰途についた。
・9月になると毎年思う。「船を出すなら九月」と。これは中島みゆきさんが作詞作曲し
た名曲のタイトルだが、真夏の喧噪が過ぎた9月がやってくると、この曲を聴いては自
分の「この先」を考える。
・30代後半で敢行した離婚も、シングルマザーで子どもを育てる覚悟を決めたのも9月
だった。その頃の私は、まだ気力も体力も充実していたので1人で船をこぎ出しても荒
波など負けないし、暗礁に乗り上げても大丈夫だと思っていた。
・40代、50代の9月は、仕事と育児と介護で気力・体力とも減退し、何よりも時間が
なかったので、新しい船を出すのは諦めた。
・近ごろ、「人生100年時代」とか「女性活躍社会」と、シニアと女性には大きな可能
性があるかのように言われている。皮肉屋の私は「所詮は困った時のシニア&女性頼み」
と思っているのだが、それでも母を見送り、穏やかな日常が戻ったこともあって、私に
もまだ少し可能性が残っているような気がしてきた。
・ところが猛暑を侮っていたのと、体力を過信していたせいで体調を崩したことから自信
喪失し、これでは小舟さえ出せないと失意の夏を過ごした。そして9月がやってきた。
・今年の船はちょっと趣が違う。勇猛果敢にひたすら前に進むのではなく「退路=逃げ道」
を断つために船を出そうと思っているのだ。
・こんな私にも、仕事もあれば良き友もいるのだから幸運に恵まれていることは否めない。
しかし、どこか柔弱な自分に甘んじてる気がするのだ。先方から退陣や退却を迫られる
のは時間の問題かもしれない。ならばなおのこと、退去する潮時を視野に入れ、やれる
うちはやるのだと覚悟をきめなければなるまい。
・大きな被害をもたらす台風や地震、日々拡大する経済格差が教育格差を生んでいる現状
を思うと、いたいけな赤ちゃんの顔を正視できない。東日本大震災後は特にそういなの
だが、どこの誰かも分からない、街で行き合う赤ちゃんに向かって「ごめんね。こんな
ふうになったのは私たち大人の責任よね。大変な人生になるかもしれないけれど、頑張
って生きてね」と、心の中で謝っている。
・自分に子どもや孫がいようがいまいが、次世代を担う子どもたちのために私たち大人世
代に何ができるかを考えさせられた。人生の終息を意識しての「自分磨き」も大事だが、
残存パワーを使って「世の中磨き」もしなければなるまい。
・父が大腸がんで亡くなったこともあって、50歳を過ぎてからは毎年大腸の内視鏡検査
も受けている。人間ドックのメニューには胃の内視鏡検査を入れてあるのだが、胃と腸
の検査が同時だとつらいので、大腸の内視鏡検査は日をおいて受けることにしている。
・大腸内視鏡検査は検査前に経口腸管洗浄剤を大量に飲まなければならず、これがイヤで
検査に行かない友人も多いが、私は苦にならない。一時は1.5リットルに減ったのだ
が、前の方が飲みやすいということで再び2リットルに戻ってしまった。ただ、味はた
しかに良くなった。
・この3年ほどは、大腸から5つ、6つのポリープが見つかって、検査後数日間は病院指
定のスープとおかゆを食べ1週間安静を命じられるなど、波乱含みの越年行事になって
いる。しかし、これも来る年を元気に過ごすための「関門」だと思って謹んで受け入れ
ている。
・私の平均睡眠時間は20代から3時間程度だ。幼少期から10代半ばまで病床に就いて
いることが多かったせいで、元気なうちは「起きたきりでいよう」と決めているのであ
る。しかし、還暦を過ぎてから周りが「もっと寝なきゃダメ!」とうるさいので5時間
に増やすことにした。しかし、5時間近く寝て、目が覚めると「こんなことをしてはい
られない!寝ている時間がもったいない!」と、後悔ととともに飛び起きてしまうので、
いまだ3〜4時間睡眠という日も少なくない。
・私の仕事周辺を見回すと、自分のやりたいことを実現させている人はみなショート・ス
リーパーだ。特に還暦や古希を過ぎた著名な人たちは数時間睡眠をものともしない。
「なんだかんだ言っても、能力は劣化しているからね。身体が自分の思いに追いつくに
は時間が必要なんだよ。それには寝る時間を削るしかないんだよね」と、みんな同じこ
とを言う。
気をつけよう、同世代、あるある!上手に年をとろう
・定年退職して1年後に起業した女性が、ため息をついてこう打ち明けた。私が会社を立
ち上げたと聞いて、「会社を創るカネがあるんだったら優雅に習い事でもすればいいの
に」とか、中には”女のくせに”と言わんばかりに「仕事漬けの人生なんて君の不幸な
女だな」とか「頂上ばかりめざさないで下山の素晴らしさを味わう時が来ているんじゃ
ないか」と、言ってきた男性が何人もいたという。こういうことを言ってくる男の人っ
て、自分を有能だと思っている人が多い。男たちが嫉妬や羨望に誘導された「葛藤の日
々」を乗り越えるには相応の時間、おおむね定年から3、4年はかかるみたいだ。
・なので私の周りにいる「アラ古希」男たちの多くはもう他人のことなど気にはしていな
い。誰に何を言われてものんびり悠々自適の毎日を送っている人もいれば、「70代で
上場するなんてどうかな?」と起業家をめざしている人もいる。「残りの時間を考える
と他人の人生をとやかく言っている場合じゃないよね。これからは周りなんか気にしな
いで好きなように自分の人生を楽しまなくきゃ!」
・団塊世代の周辺で最近話題になっているのが「年齢同一性障害」という言葉だ。「生き
ている限り青春」と思っている団塊世代は年をとった自覚がなく、年齢と行動形態が伴
っていないという意味なのだという。試しに周りの友人たちに聞いてみると、平均して
実年齢より10歳から15歳は若いと思っているみたいだ。男たちの多くは「この俺が
古希だなんて考えられないんだよね。感覚的には40代中盤か、行っても50代だな」
と、照れもせず平然と答えるのである。
・またある時、新幹線の中で、3人連れのどうみても還暦過ぎの女性たちが、10歳年下
の男性と結婚した芸能人の話をしながら「何歳まで年下ならOK」という話をしていた。
あなたがよくても相手はOKではないだろうと思いながら聞いていたのだが、真面目な
顔で言い合っているので笑うに笑えなかった。現実の話ではないのだから咎め立てはし
ないが、周囲に丸聞こえの大きな声で話しているさまを見て、彼女たちは「鏡を持てい
るのかしら」という思いに駆られた。
・若い気分は大切だと思うが、同時に自分を直視することも避けてはいけないと思うのだ
が、保守的すぎるのだろうか。
・昔は優しい面長美人だった人が、何かの拍子に鬼のような形相になったり、はたから見
ると幸福を絵に描いたように見える人なのに、突然、意地悪な顔で他人を中傷してみた
り・・・。顔のシワやシミは鏡で発見できても、心の奥底に潜む邪念は自分の目で確か
めるのは困難だ。
・「好々爺」と言っても「好々婆」と言わない。「鬼婆」とはいっても「鬼爺」はいない。
つまり、女性がおだやかに年をとるのは相当難しいということなのだろう。
・音楽、映像、広告に関わっている同性代の男性3人と飲み会を開いた。私を加えた4人
の平均年齢は69歳だ。お酒が回ると誰からともなく「働き方改革」って行き過ぎてい
ると思わない?」という話になった。最近、旧世代の制作関係者の間でしばしば話題に
なっている。
・当然、長時間残業は是正しなければならない。しかし「24時間戦えますか」で生きて
きた彼らからしたら「一律に就業時間を短縮すれば解決するのか」という疑問が拭えな
いらしい。古希を迎える年になっても、新しいものを創造するためなら徹夜をいとわな
い男たちは、最初の頃は周囲を慮ってヒソヒソ声で話していたが次第に大声になった。
・最近読み終えた本で、私がハッとさせられたのは、「学校も親も、「頑張れば報われる」
という戦後の神話を信じていて、それを押しつけてくる」という言葉だった。「頑張れ
ば報われる」という価値観は、今の私にも歴然とあるからだ。
・競争をあおられながらも、友情が大事だと言われる。矛盾している。あまりにも競争を
あおられると、劣っているやつは排除していいというメッセージとして受け取ってしま
う。努力していないんだから、と。
・受験戦争の勝者だって安心なんかしていられない。ちょっとの挫折で自分を責め、壊れ
ることでしか自分を守れない、と語る。
・団塊ジュニアの生きづらさは、団塊親の結婚生活を色濃く反映している気がする。結婚
に不全感を持っている団塊母は、子どもを支配しようとしたと。明治・大正生まれの親
たちの被害者だと思い込んでいた団塊母がいつしか団塊ジュニアの加害者になっている
と、団塊母の「責任」を指摘する。
・「総括」好きの団塊世代はあるが、それもそろそろ制限時間ギリギリだと思う。それな
らなおのこと若い人と語り合い、残された人生の中で「してはいけないこと」を考える
べき時が来ていると感じる。 ただし、語り合うべき「若い人」とは、血のつながった
娘や息子ではなく、非血縁の若い人に限った方がいいと思う。双方の心に終生の傷跡を
残さないためにも。
・年をとっても動くのはいいことだし、何でも積極的に体験するのも素晴らしいことだと
思う。しかし、自分の立っているところだけを見ていないで、少し外側、せめて半径1
メートル程度は視野に入れていないと、世の中のスピードに乗り遅れると思った。
・「暴走老人」がしばしばニュースに登場しているが、最近はあまり耳にしなくなった。
そんな中、近ごろ気になっているのが「暴言」とも「妄言」とも違う、聞くに堪えない
「猥言」を口にする「アラ古希」男性が増えていることだ。「猥言」とは耳慣れない言
葉だが、みだらな言葉という意味で、簡単に言えば「下ネタ」のことだ。
・若い頃から下品な発言が多かった人なら「またか」と思うが、これまでそんなことはお
くびにも出さない、真面目を絵に描いたような男性が口走るので仰天してしまう。
・組織社会や家庭に縛られていた時には封印されていた言動が、仲間内の旅先で解放され
たのかと思えば、哀れにも感じられる。
・我が団塊世代の男たちよ、昔はキザな台詞も甘い歌詞も似合ったのだから、時間がたっ
ぷりあるのなら映画を見たり小説を読んだりして、もう少し洗練された会話を学んでく
だされ。
始まれば終わる、未練は捨てよう
・最近「人生100年時代」というフレーズをよく耳にする。これも年金受給を遅らせた
いのと、高齢者にもできるだけ長く納税者でいてほしいという経済中心社会の思惑と直
結している気がして面白くない。政府は、元気なシニアを労働力人口として本気で期待
しているのか、それとも一瞬おだてて保有資産を供出させたいだけなのか。
・年齢は「生きた時間なのだから」と割り切って、こだわるのはやめた。働けるうちは働
き、税金を納められるうちは納めて、少しでも次代を担う若い人の一助になりたいと思
っている。
・最近、高齢者の免許証自主返納が盛んに推奨されているので、私も返納を意識はしてい
る。しかし、教習所での日々は、今も私を支えている「意地」と「根性」の起源という
気がするだけに、あっさり返納するには未練もあるのだ。更新された新しい免許証を手
に、意気揚々と運転試験場の玄関を出たら、高齢の男性が案内係に「今日で失効するの
で返納に来たのですがどこに行けばいいですか」と尋ねていた。手続きに向かう男性の
さばさばした後ろ姿を見ながら、私も次の更新までに自主返納することを決意した。
・「全てのことは始まりがあれば、終わりが来るのは必定」と思っている。楽しかった日
々は心に刻み、開いた扉を閉めて、後は振り返らないことにした。目の前の扉を閉じな
いと、次の世界につながる新しい扉は開かないだろうから。
・「空の巣症候群」は、これまで人生の大半をささげた子どもが巣立ったことで肩の荷が
下りると同時に親の役割が失われ、孤独感や絶望感にさいなまされる一過性の抑うつ症
状だ。
・「健康長寿の心得」は、人生の後半の60歳からは腹八分、70歳からはやったことの
ないことを創め、80歳はからはよく歩き、できるだけ若い人と接する。90歳になっ
たら心の赴くままに行動し、100歳からはよき友を持って、あるがままに生きるのだ
という。
・かつては88歳までは生きたいと公言していたのに、何が何でも長生きしたいとは思わ
なくなった。「私はまだまだ頑張るわよ」と、思ってたのに、最近は無欲とは言わない
が欲望が薄れてきた気がするのである。果たして私はこのまま欲望が萎えたまま人生最
期の港まで行き着くのか。それともいつかまた突然欲望に火が点くことがあるのだろう
か。
・有るか無きかは分からないが、願わくはあと一回くらいは、「名残り欲望」に火が点る
瞬間を見たいと思う。そのためには、身体の補修・修繕を繰り返してでも、元気でいた
いし、元気を阻むものは極力排除したい。
・20歳の私は、平凡な人生を変化のない日々と受け止めていた。元々、波瀾万丈こそ人
生の醍醐味、凪いだ海より疾風怒濤の荒海の方が好きだったから「退屈な毎日なんてご
めんだわ」という気持ちあったような気がする。今なら「平凡」も「非凡」も人生とい
う大海の中では大した違いはないと思うし、むしろ「平凡」を貫くことがいかに大変か、
身にしみてわかるのだが・・・。
・持病のブシャール結節とへバーデン結節という指の関節が腫れて激痛の走る病気が、こ
こにきて急速に悪化した。これまでの約1年半は左手の中指と薬指が痛かったのだが、
最近は痛みが右手に移り、右手の人差し指と中指、薬指の3本が使えなくなった。特に
中指は第2関節が粉砕し、指が曲がらないまま固まってしまったので、支柱を失いペン
を持つことも箸を持つことも困難になったのである。
・特に同性代女性に多いのだが、「そんなことも忘れたの?あなた大丈夫?」と、当方の
「老朽化」をあざけり、自分の若さを誇示する人がいる。しかし、これも時間の問題だ
と思う。嘲笑した人も、ほどなく仲間入りするはずだからだ。
・長く介護生活をしていると、女は女性性」(セクシーさ)を消失させてしまうと言われ
ているが、私も急速に「無性化」が進んでいる。この分では、私も恋とは無縁の生涯に
なるのは必至だ。でも、負け惜し半分で言わせていただけば、やっと手にした自由で気
楽なお独りさまライフを、男1匹くらいで手放すのは惜しいと思っているのである。
お独りさまは寂しくなんてない
・大人数の場合はシンプルに多数決で決められるが、旧友や親しくしている数人とお金に
関係する決定をする時、多数決では決めにくい。長年つき合ってきた友人同士でも、年
齢を重ねるに従っておのおのお経済事情が違ってくるので、「せっかくの京都に来たの
だから、奮発して京懐石を食べましょうよ」と、屈託なくは言えないのである。当事者
が数人の場合は、最も低価格なものを推す人の意見に従うのが「平和的解決策」になる
とされている。
・最近目立って増えているのが夫婦間の金銭感覚のズレについての悩みだ。金銭感覚の違
いは生まれた時の環境や親の教育などが影響しているので、ちょっとやそっとでは直ら
ないそうで、離婚に至るのも珍しくはないという。
・私が若い頃は、女の一人旅は失恋の果ての傷心旅行ではないかと疑われ、旅館やホテル
の人から自殺を警戒されたりしたものだが、最近は女性の一人旅は部屋をきれいに使っ
てくれると好評で大歓迎なのだという。食べたいものにも気を使い、買いたいものも我
慢するくらいなら、歓迎される女一人旅の方がずっと楽しい。
・女友達は娘が結婚して家を出て行ってから約10年、ずっと一人旅だという。交通機関
も宿泊も予約は旅行代理店に任せるのだという。行けるかいけないかを考えずにリクエ
ストだけする。自分でやるとホテルが取れなかったり電車が取れなかったり、何か一つ
でもつまずくと行く気が失せてしまう。旅行代理店に頼めば、プロだからうまくやって
くれるという。行動的な彼女のことだから、自分でプラニングしていりばかり思ってい
たのに、旅行代理店を利用しているとは意外だった。
・年も年なのだから格好をつけるところと、格好なんかつけないでやってもらえることは
誰かにやってもらうところを、その都度選べばいいという。交通機関と宿泊先は代理店
任せだが、現地の美味しいものだけはスマホで検索して、自分で予約することにしてい
るという。
・路頭に迷わないように交通機関と泊まるところだけは確保しておいて、旅の中身は自分
流に楽しむというアレンジ型フリープランは、「安全な冒険」を楽しみたがる団塊世代
らしい旅だ。
・老人ホームではスタッフが何でもやってくれるから、あまり早く入ると老化がどんどん
進むとか。ギリギリまで独り暮らしをしたほうがいいらしい。私は元気なうちに介護付
き老人ホームに入って、そこをベースに仕事をしたいと思っている。
・老いても人との適度な距離感をとれることが大事だと思っているので、個として生きて
きたお独りさまの入居を原則としたい。もちろん男性もOKだが、関係が固定化してい
る夫婦はご遠慮願って、入居後にそこで出会った男女が恋人同士になるのは拒まないと
いうのはどうだろう。
・「寝たきりにならないための方法」というテレビの番組で、70代の夫婦のそれぞれの
生活をドキュメントで紹介した。夫はオーキングをしたりストレッチをしたりと、毎日
のように体を鍛えている。一方、妻は運動は苦手で手芸教室を通っている。ただ、習い
事それ自体より仲間とのおしゃべりをしている時間のほうがながいみたいだ。この夫婦
のこの先、どちらの「寝込み率」が低いか。結果は運動好きの夫より、ろくに運動しな
い妻の方に軍配が上がったのである。
・運動より人とおしゃべりをしている方が脳は活性化する。結果として若いし元気だとい
う。
・運動もそうだが、禁煙や肥満解消より人とのつながりを持っている方が、心臓病や認知
症、筋力低下にならないという調査結果があるという。それもできれば旧知の人ではな
く初対面の人と会って会話をするのがいいらしい。
家族ってなんだっけ
・最近よく耳にするのが、30代から50代にかけて家庭を放り出した「恋をする夫たち」
も年をとって体が弱り出すと、妻のもとに戻ってきているという。一時は「火宅の人」
を気取っていた男たちも若さを失い、恋に見放されると、帰り着くところは、慣れ親し
んだ妻のいる家しかないようなのである。
・夫の婚外恋愛に悩んでいる若き女友達には「彼を好きなら待ちなさい。男は行くところ
がなくなると必ず戻ってくるから」と、助言することにした。ただし、帰ってきた夫は
相当ヨレヨレになっているけど・・・。
・一方、恋をしているわけでもないのに、昨今は家に帰りたがらない若い夫が増えている
のだとか。育児に積極的な「イクメン」が増えている一方で、育児・家事が苦手だった
り、イヤだったりして、自宅に帰らず本屋やカフェに立ち寄るなどして街をさまよって
いる通称「フラリーマン」が急増しているらしい。
・外をフラついている夫たちは「1人になる時間が欲しい」「家は子ども中心で居場所が
ない」「自分がいるとかえって邪魔になると思って」などと答えていた。一方、それを
聞いた妻たちは「フラフラしていても24時間365日、子育て中の私にそんな余裕は
ないのよ!」と激怒していた。
・数年前までは「絶対に子どもの世話になんかならない!」と豪語していた女友達が、近
ごろは「子どもの世話」を期待している感じがするのだ。娘がいる人は「頼りになるの
はやっぱり娘よね。息子の奥さんに面倒を見てもらうのはイヤだものね」と、本音を吐
露したりするのである。
・少子高齢化に歯止めがかからないうえに、国は財政難から病院や施設の新設を抑制し、
在宅医療、自宅での介護が推奨されている。だからといって、子どもが介護の担い手に
なるのでは、私たちの親世代と同じになりかねない。
・「子どもの世話にはならない!」と、言い切っていた頃の気概をもう一度思い出して、
どうしたら次世代に負担をかけないでこの先を生きていけるのか。改めて「自立」を考
えるべき時が来ていると思う。
・息子が結婚して以来、浮かない顔をしていた女友達と久しぶりに会ったら、とても元気
になっていた。孫でもできたのかと思ったら、孫どころか全く逆で、離婚したのだとい
う。独り暮らしになった息子の家まで片道1時間以上かけて掃除や洗濯をして行ってい
るのだという。彼女は、息子の精気まで吸い取ったかのように生き生きとしている。
・考えてみれば、私の周辺には独立して別に住んでいる息子の家に行って掃除をしてくる
母親が結構いる。娘たちは母親に向かってはっきり「NO」と言うらしいが、息子たち
は留守の間に母親が来てもあまり嫌がらないらしい。それどころか、中には母親の「清
掃来訪」を心待ちにしている息子もいるのだという。
・嬉々として息子のことを語る女友達を見ながら、彼女の存在が息子の離婚の遠因になっ
ている気がしないでもなかった。
・離婚したことも「お独りさま」になったことも後悔してはいない。でも、最近周りのシ
ニア夫婦を見ていると、途中さまざまあっても長く一緒にいるのは悪くないかも・・・、
と思う。
・ここに至るまでの間、当の妻たちからは、夫との愚痴を聞かされたり、離婚危機で仲裁
に入ったりということもあったが、妻が65歳を超えたのを境にそうした話はパタッと
なくなった。2人とも年をとって互いに支え合うしかないという「実利」に気づいたの
かもしれないし、ここで別れても新しいパートナーとの次なる展開は望み薄という諦め
もあるのかもしれないが「古夫婦」ならではの良さを感じることが多くなった。
・性や愛を超越した枯淡の境地とでも言うのだろうか、互いの欠点をのみ込んだ上で相手
を思う気持ちがあるという関係は同性の親友同士みたいだ。現に夫婦間の話を聞いてい
ても、若い頃のノロケ話と違って生々しさがなく聞きやすい。
若い世代に驚き、学ぶ
・昔は、男性が自分の異性交遊を自慢げに話すことはあっても、女性は特定の恋人がいて
も手一つ握ったことがないようなふりをする「カマトト娘」が多かった。カマトトが死
語になった今、若い女性は「つき合った男の1人や2人、いない方がおかしいですよ」
という感じだ。私の根幹には保守主義の種が宿っていて、男女間については堅苦しい考
え方を持っている。しかし、若い女性が堂々と男性との関係を話す姿は何度か聞いてい
るうちに慣れてきて、小気味いいと思うようになってきた。
・雑誌は「雑」の権化で、取材記者はいろいろなものが入り交じった雑多な世界から何か
を引き出す技が要求される。そのため広く世間に意識を張り巡らせておく、というのが
雑誌文化の基本だ。それなのに最近の若い取材記者は、ニュースをウォッチするのも
Web頼み。しかも自分の関心事以外はクリックもせず、無益な雑情報として切り捨て
ているような気がする。
・一方、雑誌で育った団塊世代は雑学の楽しさも雑草のたくましさも知っている。正統や
権威と無縁の真理は「雑」の中に潜んでいるとさえ思っている。こうした「雑の世界」
をすくい取る力がなくなると、単に粗雑な神経の人だけが増えて、旧世代はますます生
きにくくなりそうだ。
・最近アメリカに視察旅行に行って感じたのは、総じて、アメリカ人の「人間力」が随分
と衰退していることである。全てコンピューター頼みにしたために人間の素の力が消失
してしまったようで、ひとたびトラブルに直面すると信じられないぐらい時間がかかる。
一方、コンピューター源泉の地ともいうべきシリコンバレーだけは人材と富が集積して
いて、衰退とは無縁のようだった。この10年で日本人の留学生は減少し、代わって中
国人と韓国人留学生が激増しているという。
・テクノロジー頼みで人間力が弱まっているアメリカと、他を圧する強烈な人間力で世界
を切り拓いている中国の間で、私たちはどこに活路があるのだろう。米中間は今後も綱
引きを繰り返しながら微妙な関係が続いていくと思うが、シリコンバレーを見ていると
日本人の出番はどんどんなくなっていくような気がした。