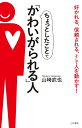ていったらよいのか。そういう問題に直面した時に参考になるそうな本である。
今の時代はともかく勝ち負けにとても拘る風潮がある。「勝ち組」とか「負け組」と
かという言葉が流行したのもそういう時代だからであろう。しかし、人生全体を見たと
きに、人生半ばにおいてその人生が「勝ち」なのか「負け」なのか簡単に決めることが
できるのだろうか。「負け」ていた人生が最終的にはとても幸せな人生になる場合もあ
るし、「勝った」と思っていた人生が途中で思いがけない転機に見舞われて悲痛な人生
に終わってしまう場合もある。
そもそも、何を持って「勝ち」や「負け」と決めるのか。単に金持ちになったり出世
すれば「勝ち」なのか。もしそうだとすれば、多くの人が「負け」の人生となる。なぜ
ならば金持ちになったり出世できる人は全体のごく一部の人たちだけであるからである。
それに金持ちになったり出世できたりした人たちは、ほんとに幸せな人生なのだろうか。
幸せな人生を送るにはどういう生き方をすればいいのかのヒントが、この本の中にある
ような気がした。
・人に負けないようにと自分を励まし、人に勝つ方法はないかと知恵を絞って画策する。
自分の目標に向かって努力を続けていくのであるが、あまりにも熱心に取り組んでい
くと、前進ばかりを考える傾向になる。人に打ち勝つことばかり考えて、自分自身の
能力や立場を忘れてしまう。周囲の状況までわからなくなる。
・時々立ち止まって、横に目をやったり、後ろを振り返ってみる必要がある。自分を客
観的に観察して、自分の「実態」の把握に努めるのだ。自分が現在していることと、
世の中の流れや世間の人たちの考え方、それに自分の得意なところがマッチしている
か。がむしゃらに勝ちを目指しているために、無理をする結果になり、成果が上がっ
ていないのではないか。
・下手な努力は休むというよりも後退するものと同じ結果になっている場合がある。原
点に返って、人生で自分が最終的に求めているものは何かを考える。それは平和で幸
せに暮らしていくことではないか。出世や金や健康、それに豊かな人間関係なども、
そのための手段であるにすぎない。
・人生は過程である。日々の生活を充実させる必要もある。余裕を作り出して楽しむ術
も覚えなくてはならない。道草を食うのを無駄として拝するのは間違っている。それ
は、余力を蓄えると同時に、自分のバランス感覚を養成し調整する機会でもある。
・自分は自分以上にはなれないし、自分以下にもなることもない。その点を悟れば、そ
れは大いなる「諦め」につながり、そこから自信が醸成されてくる。
・人生においては、努力を続けていかなくてはならないが、無理をしてはいけない。
強大な力に抵抗して自滅する結果になるのは、得策とはいえない。大きな圧力や世の
流れに対しては、「柳に風と受け流す」。突っ張って無駄な努力をするよりも、上手
に受け流すのである。「柳に雪折れなし」で、フレキシブルに対応すれば、耐える力
も少なくてすむ。その間に雌伏しエネルギーを蓄えておけば、いざというチャンスが
到来したときは、全力投球で雄飛を図ることもできる。
・柳のように臨機応変をモットーとして、しなやかに生きていく。人生を短期決戦の連
続にしてはならない。長期にわたる平和維持運動として位置づけていく。太く短くよ
りも「細く長く」を目指す。
今まで生きているだけでも、勝っている証拠
・赤ん坊に始まり幼児、少年、青年を経て大人になったのは、幾多の試練に耐えて辛苦
を重ねて生き抜いてきた証拠だ。人によって程度の差はあっても、数多くの競争にお
いて打ち勝ってきたのである。負けた競争もたくさんあったが、それ以上に勝った競
争が多かった結果にほかならない。
商売上手に学ぶ、負けの成功哲学
・どんなに全力投球しても、思い通りの結果が出るとは限らない。そこで悩んでいない
で、人生を続けていくことだ。人生のおける禍福は予測できない。「塞翁が馬」なの
である。
・負けるのは後退であるが、長い人生という期間から見て大きな視点に立てば、ちょっ
とした変化でしかない。一休みする結果にもなり、自分の進路について間違っていな
いか確かめたり自分を鍛えたりする機械にもなる。
・人生の常勝はありえない。負けたのをいつも不本意に思うのは、精神衛生上もよくな
い。
手柄を横取りする上司は、馬鹿を公表している
・部下より自分が上である点を、ことある度に見せつけようとする上司がいる。横柄な
口をきいたり、押し付けがましい態度に出たりする。
・にもかかわらず、ことさらに上司ぶった言動をする人は、人々が自分のほうが劣って
いると見ているのではないか、という恐れがあるからである。すなわち、自分自身に
上司としての器量がないことを見とめている証拠でもある。
・そのような上司の下で働いている者としては、運が悪かったと諦めて辛抱していれば
よい。そのうち「失脚」するので、自分が追い越していく結果になる。
・上司の部下に対する役目は、適宜に監督して、よりよき人材に育て上げることにある。
だが、指揮し監督する点に重置き置くと、つい専制的な色彩が強くなる。そうなると、
気の弱いものは萎縮してしまい、本来持っている才能や技能を十分に発揮することが
できなくなる。それよりも指導育成に焦点を合わせてみると、部下の能力を伸ばす方
向へ進むことになるので、部下のやる気も向上する。
・部下と競い合うなどという考えが少しでもあったら、自分の成長は止まると覚悟しな
くてはならない。部下を励まし後押しして、立派な業績を上げさせるようにさせる。
そのとき、その手柄をすべて部下のものとして、褒め称えるのが、重要なポイントだ。
部下はどんどん褒めて調子に乗せたほうがトク
・人と競うのではなくて、人の勢いを盛り上げていって、その勢いに自分も乗っていく
ほうが得策だ。つならない意地を突っ張って対抗意識を燃やし、無理をする必要はな
い。自分の調子がよくなくエネルギーが枯渇していると感じるときもある。そのよう
なときは、雌伏徹するのも一つの方法である。
休みたいときは休む
・どんなことについてもいえることであるが、何かが悪くなったら、まずそれを直すこ
とに全力を挙げなくてはならない。忙しいからなどといって改善の作業を中途半端に
していたら、悪い根が絶えることはない。
・自分の心身に関する「悪」についても、その撲滅と原因の根絶を至上の課題としてお
く必要がある。すなわち、病気のサインが見えたら、直ちにその「撲滅」を図るとい
う姿勢だ。
組織は社長が抜けても動くようになっている
・組織としては、個人が組織を思っているほどには、特定の個人を頼りにしたり思った
りしてはいない。ある意味では組織は非常なのである。したがてって、組織と自分
とは対等であるという意識を失わないで、組織とつきあっていく姿勢が必要となって
くる。
・病気になっても組織がしてくれる配慮や世話には限界がある。たとえ、組織のために
無理をして死に至ったとしても、葬式の場で賛辞を呈してくれて、霊前に大きな花を
供えてくれるだけだ。自分の人生に焦点を当て続けていれば、自分のペースを守って
仕事とも取り組むことになる。病気であったり気が進まなかったりしたら、仕事を休
むのは当然だ。
上司と同じ趣味は持たない
・すすめられても、上司とは同じ趣味の道には入っていかないのが賢明だ。
・趣味の世界であるといえども、というよりも個人色の強い世界であるかれこそ、聖域
の色彩が強い。「観客」として見る立場を貫き、自分も「舞台に上がる」ことなどは
考えないほうがよい。それまでの、その人との人間関係にあったバランスが大きく崩
れる結果になるからである。
他人の好みにはボジティブに、しかし小さく反応する
・人が強く好き嫌いの感情を示していることに対しては、論評は差し控えるのが賢明だ。
自分に強い利害関係があるような場合でも、本気になって議論などをしてはいけない。
いたずらに相手を敵に回すことになるからである。
英語の能力と教養の有無はまったく関係ない
・英語を流暢に話すということは、技能の一つであるにすぎない。ゴルフがシングルの
腕前だというのと同じであって、賞賛はするものの、自分がそうでないからといって
恥ずべきことではない。
・英語が話せても、頭が良くなかったり品格がなかったりする人は大勢いる。英語の能
力と教養の有無も、まったく関係ない。英語がわからなかったら、日本語で話してみ
ればよい。要は、毅然たる態度で正しい自国語が使えるかどうかがポイントである。
高望みしてこだわっていても、足踏みしているだけ
・現実の世界の中では、完全にしようと思ったら、何一つ選択することはできない。功
罪をいろいろと比較検討すればするほど、迷いが生じてくる。どこかで思考を停止さ
せて、一か八かの選択するほかない。その思いっきりをどこでするかが、成否の分か
れ目という結果になる。
自分の才能に見切りをつける
・自分の才能について高望みをしてはいけない。日々向上しようと努力はするものの、
現在の時点における能力については、諦めるのが賢明だ。そもそも、諦めるというの
は、現実を「明らめる」すなわち明確に見定めて、そのままに受け入れることである。
世の中には100点というものがあっても、自分は70点であることを納得するのが
肝要だ。
忠実なるイエスマンに見習うべきこと
・大きな組織を動かすときには、偉大なるトップのすぐ下に、恥も外聞もないイエスマ
ンがいると、非常に効果的である。
・専門的な知識と技能を持ったスペシャリストが高く評価され、ゼネラリストがバカに
される傾向がある。一般的なことをそこそこにしかできないゼネラリストが駄目なの
は当然だが、ちょっと勉強さえすれば何でも成し遂げることのできる人は貴重な存在
だ。
・専門的な知識が技能といっても、狭い分野のものであれば、日進月歩の昨今において
は、すぐに廃れたものになる。コンピュータ業界で専門家といわれている技術者たち
に、絶え間なく市場に出てくる新製品に対して適切な対応のできない人が多い。
・専門化が加速していくと、視野の狭い専門家はついていけなくなる。そこで、ゼネラ
リストの素質が必要となってくるのである。
”腹を見せる犬”ほど好かれる
・人と仲良くなろうと思ったら、徐々に打ち明け話よろしく自分の弱みをさらけ出して
いくのだ。自分の周囲に張り巡らした壁が少しずつなくなっていくので、そこへ人が
入り込んでくる。弱みは人間らしさであり、それを表に出して見せるのは人なつっこ
さの表明である。マイナスであると思っていた弱みが、人間的魅力というプラス要因
に転換されるのだ。
聞き上手は説得上手
・正面から攻められると、反発しようとするのが人情だ。抑えようとされれば、跳ね返
そうとする。また、たとえどのような正論であっても、探し出そうとすれば、どこか
に弱点や抜け穴がある。そこを突いて反論することができる。
・言い負かそうとするから、角が立つのである。頭から説き伏せようと意気込んでいる
ので、人によっては、まず自分を守ろうとする。自分の殻に閉じこもって、もっぱら
防戦に努める。まずは、相手に警戒心を抱かせないことだ。
・説得ではなく「話し合い」をすることである。すなわち、一方的に話すのではなく、
お互いに話したり相談したりする雰囲気にしなくてはならない。それも、自分の考え
方を述べるよりも、相手の言い分を聞くほうを優先する姿勢に徹する。
親友に借金を申し込まれたら
・冷たいといわれようが、金を貸さないという勇気も持たなくてはならない。安易に金
を貸すのは、相手に対しても自分自身に対しても、一時的な気休めにしかならないこ
とに気づく必要がある。
・人が金を借りるときの保証人になるのは、持っての外の軽率な行為である。というよ
りも、暴挙であるといったほうがよい。人を助けるときは、それによって自分の生活
が大きく聞きに瀕することがない点を、きちんと見極めてからにする。自滅にまで至
る恐れのある負け戦には、加わるべきではない。
控えめであるほど、奥行きがでる
・見栄を張るのは、自分のあるがままの姿に満足していないことを示している。自分は
自分以外になりえないことを悟っていない。往生際が悪いというほかない。自分を自
分以上に見せようとするために使う時間とエネルギーがあったら、それを自分を率直
に打ち出したり向上させたりする方向に、振り向けるべきである。
・見栄を張るは、現在の自分に関して、敗北宣言をしているにも等しい。見栄を張って
も、すぐに見破られる。そうなると、自分の実際のレベルは、見栄を張ったラインよ
りも下であることが明らかになる。それよりも、ありのままを見せたりいったりすれ
ば、その控えめな態度は必ず好感を与える。そうすると、実際のレベルは、本人が示
しているラインよりもずっと上であるに違いない、と思われるようになるはずだ。
金持ちは泥棒にはならない?
・疑いの目をむけられたときは、一言の下に否定する。疑いを抱いた人の目を正面から
見据えて言うのである。相手も立派な人であれば、疑いを抱いたり信じたりした自分
を恥じ入るはずだ。
・あまりにも的外れで話にならない類いの疑いをかけられたようなときには、言葉を発
するのも馬鹿馬鹿しい。黙したままで相手をにらむがごとくに凝視し続けて、相手が
目をそらしたのを機に立ち去ればよい。まさに下司の勘ぐりなどは歯牙にもかけない
という様子を示して、毅然たる態度を保つのだ。
「損切り」は恋にも必要
・何かの成就を目前にしているときでも、大きな障害が現れてその除去が不可能に近い
と思ったら、あっさりの見切りをつける。そこで無理をして自分が谷底に転落してし
まったのでは、一巻の終わりである。
・人とつきあうとき、特に異性との交際の場合は、この点に心しておくべきだ。ここま
で付き合ったのだからと思っても、これ以上仲良くなれる見込みがないと思ったら、
大やけどしないうちに別れるべきだ。深追いをしないで、損切りをするのである。
品のない人に食いつぶされないために
・何でも屋とか「いつでも屋」とかになってはいけない。すなわち、自分の最も得意な
分野だけに限定したり、仕事をする時間の範囲を決めておいたりするのである。常に
余力を蓄えておく必要がある。さもないと、能力があってできればできるだけ「便利
に」使われることになる。
・資本主義社会においては、労働者は利益追求のために搾取の対象となる危険にさらさ
れている。油断することなく、保身についても考え続けていく必要がある。特に、も
てはやされているときが危ない。それは、一介の社員に限らず、経営者という名であ
っても、働いている限りは、資本主義社会の下では同じ労働者であって、変わること
はない。
・才能を見せるのも、努力するのも、時と場合を見極めて、ほどほどにしていくバラン
ス感覚を失ってはならない。
選挙にぜひ取り入れてほしい「マイナス票」
・企業の中であれ人々の輪の中であれ、人に嫌がられたり敬遠されたりしているうちは、
まだよい。否定的にあっても、グループの一員として認められている。ところが、最
も怖いのは、無視されることである。
・権力の悪い面に対しては、無視するのがよい。非難はおろか、批判までもしない。た
とえば、単なる数集めに等しい、昨今の選挙のやり方は、言語道断である。
どんな親でも子供にはローリスクを望むもの
・親が勝手に最も安全であると考えた道へと子を強制したときに、悲劇が起こる。人生
で一番楽しいはずである少年期や青年期を抑圧された環境の中で過ごすことになる。
子としては、まったく自由のない強制収容所の中で暮らすにも等しい毎日になるので
ある。
・人生航路の中で障害物に出合ったとき、人に迷惑を掛けないで自力で切り開いていく
自信があれば、挑んで切り崩していく。自分の力には負えない障害物と思ったら、そ
れを避ける方法を考える。障害物を取り除こうとすれば犯罪になる可能性のあるとき
は、そのような切り崩し方をしてはいけない。
上見ればきりなし、下見てもきりなし
・常に他の人を意識しながら、その先を行こうとして余分の、ないしは無理な努力をし
ても、それほど期待する結果は出ない。淡々として自分のペースを守っていくのが、
以外によい結果をもたらす。
・周囲の環境の推移や、人々の考え方の変化について、詳細に観察し参考にしていくこ
とは必要である。だが、それによって一方的に左右されてはならない。自分の目指し
た目標へ向かって、信念を持って「真っ直ぐ」に進んでいく。二点間の最短距離は直
線であることを忘れてはならない。
・上見ればきりなし、下見てもきりなし、である。現在の時点と場所において自分が置
かれている状況を、虚心坦懐に「観察」してみる。借りたものであれ所有しているも
のであれ雨風しのぐ住居があり、清潔な衣服を身に着けて、それなりに食べていける
身であれば、そこから「突発的」に上に上がっていく必要はないのではないか。
狙うべきは「人並み」と「並外れた」の間
・主張すべきは堂々と主張するのがよいとされている。だが、それを拡張解釈したり誤
解したりしている人が多い。すなわち、主張「すべき」ことを、主張「したい」こと
と、間違った解釈をしているのである。人間の欲は、そのままにしておくと際限なく
広がっていくので、主張したいことはいくらでもある。その中から、世のルールとい
うふるいにかけて、主張すべきことを選び出さなくてはならない。
心の帳簿の残高は清算しない
・貸し借りをする結果になったとき、その状態をそのまま維持することの進めである。
すなわち、人から恩を受けて「借り」ができた場合に、もちろん感謝の念は表明する
が、すぐに「お返し」」などをしないことだ。すぐに借りを返さないで、相手の厚情
を自分の心の中に刻み付ける。すぐに貸借関係を清算したのでは、縁も一緒に切れた
しまう。厚意に関しての貸借し、その残高をゼロにしないことによって、人間関係を
積極的に維持していくのである。
行過ぎた贅沢にまわりは辟易している
・贅沢が程度を超すと堕落である。健全さが失われて、人間らしい情感もみられなくな
ってくるからだ。本人は 栄耀栄華を極めていると考え満足していても、ほかの人は
羨ましくは思いながら、眉をひそめて見ている。自分のエゴのみが突出して、ほかの
人のことは気にかけないというにおいが強く感じられるからである。
・自分が必要とするものではなく、世間が高級であると考えるものを追い求める。自分
が本当にほしいと思うものではなくて、世間的な標準で上のクラスといわれるものば
かりを狙うようになる。自分の好きなものであっても、下のクラスに属するものと考
えられていたら、敬遠するようになる。それでは、精神的には極めて貧しい生活を、
部分的にであれ、強いられる結果になる。
今の日本人に品はあるか
・「衣食足りて礼節を知る」といわれている。だが、客観的には「足りて」いると見え
るときでも、当人が「足りない」、すなわちまだほしいと思っていると、逆に礼節が
失われる傾向が見られる。飽きなき欲の追求のために、ほかの人たちのことが目に入
らなくなるからである。強欲な人には、衣食が足りたと思うときはやってこないのだ
ろう。
・戦後の日本人は痩せてはいたが品があった。最近の日本人は肥ってはいるが。